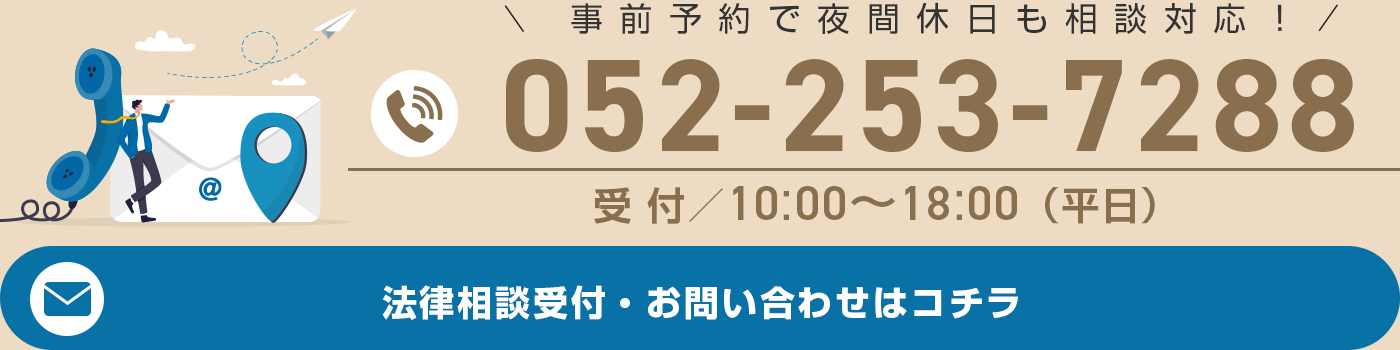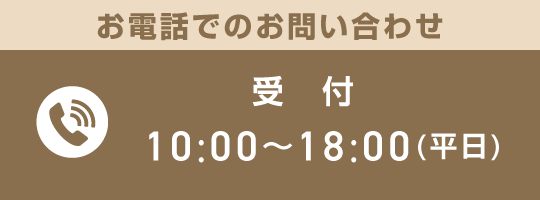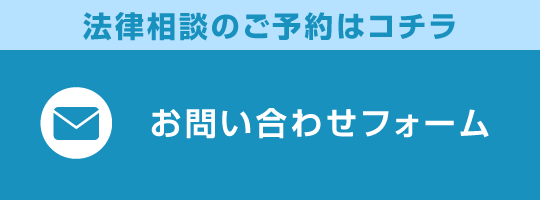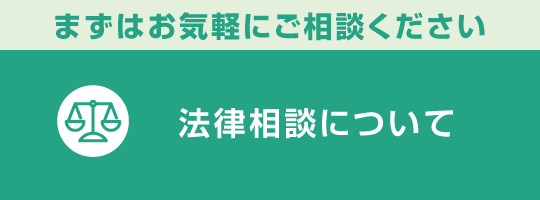このページの目次
遺留分侵害額請求の方法と注意点について弁護士が分かりやすく解説します
「他の相続人は遺言でたくさん財産をもらっているのに自分の取り分がわずかだった」
「他の人に多額の生前贈与がされており、遺産をほとんど取得できなかった」
そのような場合、遺留分侵害額の請求が可能かもしれません。ここでは、遺留分侵害額請求の方法と注意点について弁護士が分かりやすく解説します。
遺留分とは?-相続人の最低限の取り分
人は自分が死亡した場合に自分の財産を誰にどのように引き継がせるのかを遺言書によって決めることができます。
遺言書の内容は遺言者が自由に決めることができるので、極端な場合、全ての遺産を特定の誰か(親族である必要すらありません)に相続させる、といったこともできてしまうわけです。民法ではこれを遺言自由の原則などといったりします。
しかし、遺言自由の原則を貫くと、本来、相続によって遺産を取得できたはずの相続人が全く遺産を取得できなかったり、取得できたとしてもわずかの額しかなかったりして不公平な結果となります。
また、このことは遺言書の内容が不公平な場合だけではなく、被相続人が生前に多額の財産を他人に贈与していたような場合にも当てはまります。
そこで、被相続人が遺言や贈与によって自由に財産を処分できることを前提としつつも、相続人に最低限の取り分を保障することで、不公平を是正しようとするのが遺留分という制度です。
具体的には、遺留分として保障された持分を遺贈や贈与などによって侵害された場合、遺留分を侵害された人が、受遺者(遺贈を受けた人)や受贈者(贈与を受けた人)などの遺留分侵害者に対し、侵害された遺留分額(遺留分侵害額)を金銭で支払うよう請求できることになっています。
遺留分を請求できるのは誰?
民法によると遺留分を請求できるのは「兄弟姉妹以外の相続人」とされています(1042条)。
したがって、まず被相続人の兄弟姉妹は遺留分を請求することができません。
また、相続人であることが前提なので、遺留分を請求するためには、その相続において相続資格があることが必要です。
ですので、例えば被相続人に子がいる場合、被相続人の親には相続資格がありませんので、遺留分を請求することもできないということになります。
また、相続放棄をした人は始めから相続人ではなくなるので、遺留分を請求することはできません。
なお、代襲相続の場合、代襲相続人は被代襲者の遺留分を請求することができます。
遺留分を請求できる人の範囲については、別のコラムでも詳しく解説しておりますので、そちらも参考にしてください。
関連記事:「遺留分を請求できる人の範囲は?」
遺留分侵害額請求をするかどうかは権利者の自由
遺留分を侵害された場合であっても、遺留分侵害額請求をするかどうかは、それぞれの相続人が自由に判断することができます。
ですので、遺留分を侵害された相続人が、被相続人の意思を尊重して、遺留分侵害額請求をしないという選択をすることももちろん可能です。
侵害された遺留分の額(遺留分侵害額)はどのように計算する?
遺留分侵害額計算の概要
遺留分を侵害された場合、侵害された遺留分の額を受遺者(=遺贈を受けた者)や受贈者(生前贈与を受けた者)などの遺留分侵害者に請求できます。
侵害された遺留分の額(=遺留分侵害額)は、極めて大雑把にいえば、
【自分の遺留分】 − 【自分の取り分】
で計算できます。
したがって、自分の取り分が自分の遺留分額に満たなかった場合は、遺留分侵害額を請求できる可能性があるということになります。
以下で細かい計算方法を解説します(少し難しい話になりますが、適宜、具体例を用いつつ分かりやすく解説するので安心してください)。
まずは自分の遺留分額がいくらなのかを計算する
遺留分侵害額を計算するためには、最初に自分の遺留分の金額がいくらであるのかを計算する必要があります。
遺留分額は、基礎となる財産の額に自分の遺留分の割合をかけて求めます。
つまり、遺留分の金額 =【基礎となる財産】 × 【遺留分割合】ということです。
そこで以下では、「基礎となる財産」と「遺留分割合」について、順番に解説したいと思います。
基礎となる財産(基礎財産)
遺留分額を算定する上で基礎となる財産は、以下の計算式に従って計算します。
基礎財産 =【① 被相続人が相続開始時点で有していた積極財産】+【② 贈与された財産】−【③ 相続債務の全額】
① 被相続人が相続開始時点で有していた積極財産
まず、①は被相続人が死亡時点に有していたプラスの財産です。遺贈がある場合も、遺贈の事実は無視して(つまりプラスもマイナスもせずに)死亡時の財産にのみ着目します。死因贈与の場合も同様です。
例えば、被相続人が死亡時に1億円の資産を有しており、その1億円の中から誰かに5000万円を遺贈した場合であっても、①の額はもともとあった1億円になるということです。
なお、不動産や株式など評価額が増減する資産については、相続開始時点(被相続人死亡時点)の評価額によって計算します。
② 贈与された財産
次に②ですが、贈与とは無償の財産処分全般のことをいいます。財産をタダで人にあげる文字通りの贈与の場合もあれば、一般財団法人への財産の拠出なども「贈与」にあたります。
もっとも、これには期間による制限があります。
具体的には、原則として、相続開始前1年以内にされた贈与に限ります。
ただし、遺留分権利者に損害を与えることを知りながらされた贈与であれば、1年よりも前にされた贈与も含めて計算します。
また、相続人に対する特別受益としてなされた贈与(婚姻、養子縁組のため又は生計の資本としてされた贈与)は、相続開始前10年以内にされたものであれば、贈与として基礎財産に加算されます。
③ 相続債務の全額
最後に③ですが、被相続人の遺産の中に借金などのマイナスの財産がある場合は、基礎財産から差し引きます。
以下に具体例を挙げておきます。
【具体例】
被相続人Aに妻Wと子X、Y、Zがいたとします。Aの死亡時のプラスの財産は1億円でした。Aは死亡する半年前、赤の他人であるBに5000万円を贈与しました。また、Aは死亡する7年前、Xに生計の資本として3000万円を贈与しました。
Aは「遺産のうちXに6000万円を遺贈する」という遺言を残して死亡しました。他方、Aには死亡時に1000万円の借金がありました。遺留分算定の基礎財産はいくらになるでしょうか?

死亡時の財産は1億円です。AはXに6000万円遺贈していますが、これは無視します。
そして、死亡の1年以内に5000万円をB贈与しており、さらに死亡の10年以内に生計の資本として相続人であるXに3000万円を贈与しているので、これらを加算します。
他方、死亡時の借金1000万円は差し引きます。
結果、基礎財産の価格は1億7000万円(=1億円+5000万円+3000万円−1000万円)となります。
遺留分割合
基礎財産の額が計算できたら、次は遺留分割合です。
遺留分割合には総体的遺留分割合と個別的遺留分割合があります。
総体的遺留分割合とは、遺産全体に占める遺留分全体の割合のことです。
総体的遺留分は法律で決まっており、直系尊属(≒被相続人の父母など)のみが相続人の場合は遺産全体の3分の1が、直系尊属以外の相続人もいる場合は遺産全体の2分の1が遺留分になります。
そして遺留分権利者が複数いる場合は、この総体的遺留分割合を各遺留分権利者の法定相続分に従って分け合うことになります。これが個別的遺留分割合になります。
以下に具体例を示します。
【具体例】
被相続人にA妻と子X、Yがいたとします。Aは「遺産を全てXに与える」という遺言を残して死亡しました。このとき、WとYの個別的遺留分割合はどのように計算されるでしょうか?

まず、このケースでは直系尊属以外の相続人がいるので、総体的遺留分割合は2分の1です。
そして、この2分の1の総体的遺留分を法定相続分に従って各遺留分権利者が分け合うことになります。
配偶者と子の法定相続分は2分の1ずつなので、法定相続分はAが2分の1、XとYがそれぞれ4分の1ずつになります。
したがって、個別的遺留分割合は、Aが1/2×1/2=1/4、Yが1/2×1/4=1/8となります。
遺留分割合を表にして整理すると以下のようになります。
| 配偶者の遺留分 | 血族相続人全体の遺留分(注) | |
| ① 配偶者のみが相続人の場合 | 2分の1 | – |
| ② 子のみが相続人の場合 | – | 2分の1 |
| ③ 直系尊属のみが相続人の場合 | – | 3分の1 |
| ④ 配偶者と子が相続人の場合 | 4分の1 | 4分の1 |
| ⑤ 配偶者と直系尊属が相続人の場合 | 3分の1 | 6分の1 |
| ⑥ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 | 2分の1 | なし |
(注)血族相続人とは配偶者以外の相続人(血のつながった相続人)のことをいいます。同順位の血族相続人が複数いる場合は、頭数で割って計算します。
侵害された遺留分の金額(遺留分侵害額)の計算
基礎財産と個別的遺留分額が計算できたら、それらをかけ合わせて自分の個別的遺留分額が計算できます。
個別的遺留分額が計算できれば、次はいよいよ侵害された遺留分の額(遺留分侵害額)を計算することになります。
計算式は以下のとおりです。
遺留分侵害額 =【①遺留分権利者の個別的遺留分額】−【②遺留分権利者が受けた遺贈及び特別受益である贈与の金額】−【③遺留分権利者がその相続において取得した遺産の額】+【④遺留分権利者が負担する相続債務の金額】
なお、②の「特別受益である贈与」とは、婚姻、養子縁組のため又は生計の資本としてされた贈与のことをいいます。
先ほど、遺留分侵害額は大雑把にいえば【自分の遺留分】−【自分の取り分】だと説明しました。
上記の計算式のうち、①の部分が【自分の遺留分】に、②〜④の部分が【自分の取り分】に該当する部分になるということです。
1点注意が必要なのは、相続人の誰かが被相続人の資産形成に貢献していたとしても(つまり相続人の誰かに寄与分があったとしても)、遺留分侵害額の計算においては考慮されません。
以下、具体例を挙げて説明しましょう。
【具体例】
被相続人Aには妻Wと子X、Yがいました。Aの死亡時の財産総額は4500万円でした。Aは「遺産の中から4000万円をBに、300万円をWに、200万円をXに与える」という遺言を残して死亡しました。
Aは死亡時、800万円の借金を負っていました。
また、Aは死亡する半年前に生計維持のために1500万円をYに贈与していました。
Wは、Aの生前にAの事業を手伝っており、Aの資産形成に多大な寄与をしていました。少なく見積もってもAが資産形成に寄与した金額は2000万円以上になります。
W、X、YがBに請求できる遺留分侵害額はいくらになるでしょうか?

まずは、個別的遺留分の計算からです。これについては先ほど説明したとおりです。
各自の個別的遺留分額は以下のように計算されます。
W:(4500万円+1500万円−800万円)×1/2×1/2=1300万円
X:(4500万円+1500万円−800万円)×1/2×1/4=650万円
Y:(4500万円+1500万円−800万円)×1/2×1/4=650万円
W:0円
X:0円
Y:1500万円
遺言の内容から、以下のようになります。
W:300万円
X:200万円
Y:0円
相続債務800万円を法定相続分に従って負担することになるので、以下のようになります。
W:800万円×1/2=400万円
X:800万円×1/4=200万円
Y:800万円×1/4=200万円
以上から各自が遺留分を侵害された金額は以下のようになります。W寄与分2000万円は遺留分侵害額の算定においては考慮されません。
W:1300万円−300万円+400万円=1400万円
X:650万円−200万円+200万円=650万円
Y:650万円−1500万円+200万円=−650万円→0円
遺留分は誰に対して請求するのか?
遺留分を侵害された場合、遺留分を侵害している受遺者(遺贈を受けた者)や受贈者(贈与を受けた者)に対して遺留分侵害額を請求することができます。
遺留分侵害者が複数いる場合は、以下のルールによります。
- 受遺者と受贈者がいる場合 → 受遺者に先に請求する。
- 受遺者が複数いるとき、または受贈者が複数いる場合においてその贈与が同時にされたものであるとき → 受遺者または受贈者にその目的物の価額に応じて請求する。
- 異なる時期にされた贈与の受贈者が複数いるとき → 後の贈与の受贈者から順に請求する。
遺留分侵害額請求の手続きは?
遺留分侵害額を請求する場合、まずは弁護士を介して相手に通知書を送り、任意での交渉から開始するのが通常です。
任意交渉で合意に至らない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申立て、調停の中で話し合いを進めていきます。
それでも、合意できない場合は、遺留分侵害額請求訴訟を提起して、裁判所に判断してもらうことになります。
遺留分侵害額請求は期間制限に注意!
遺留分侵害額請求には期間制限があります。
すなわち、遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しない場合、遺留分侵害額請求権は時効によって消滅すると定められています。
1年間という極めて短い期間制限が設けられており、この期間をすぎると遺留分侵害額請求をすることができなくなります。
遺留分侵害額請求をお考えの方は、早めに弁護士にご相談ください。
遺留分請求は弁護士に相談を
遺留分侵害額請求は、侵害額の計算など極めて高度な専門知識が必要な分野です。また、相手方が遺留分について必ずしも知識を有していない場合も多く、弁護士を介した説得、交渉の必要性が高いといえるでしょう。
遺留分侵害額請求をお考えの方は早期に弁護士に相談されることをおすすめします。