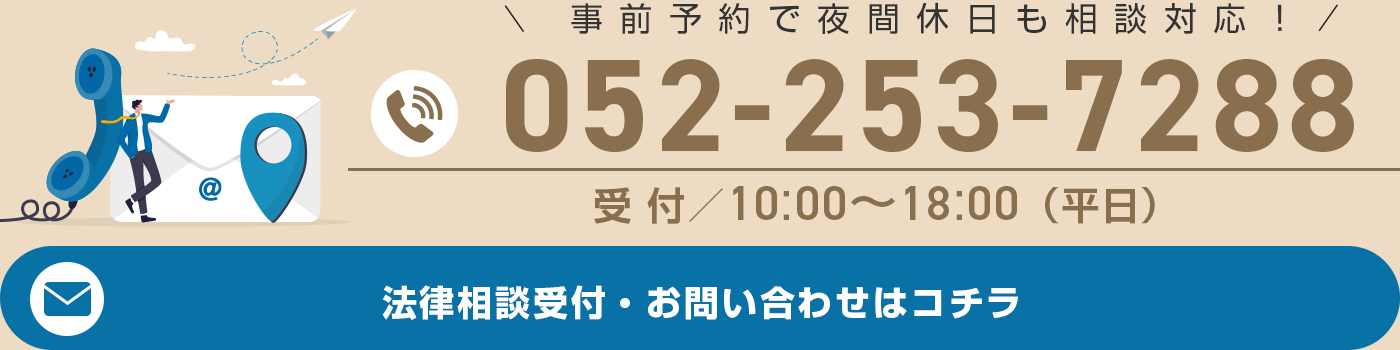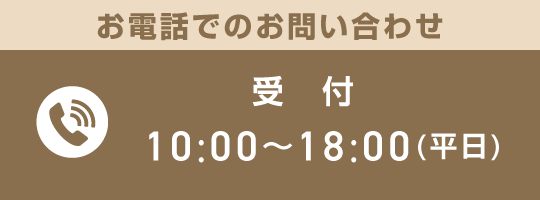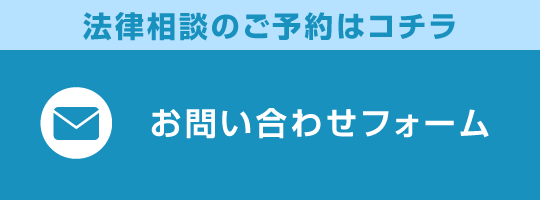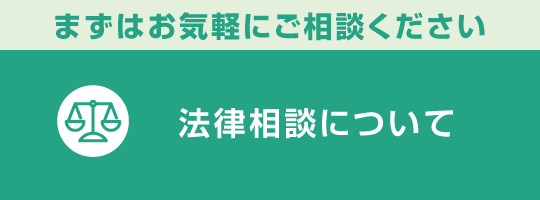ここでは「起訴されて前科がついてしまうのを避けたい」という方々のために、刑事事件における「不起訴」とは何か?また、不起訴になるにはどうすればいいか?を詳しく解説します。
このページの目次
不起訴とは何か?
「不起訴」の反対は、もちろん「起訴」です。
「起訴」とは、検察官が裁判所に対して、刑事事件を裁判所で審理するよう求めることをいいます。
したがって、「不起訴」とは、その反対の「刑事事件について裁判所での審理を求めない」という検察官の決定のことをいいます。
不起訴になると事件はそこで終結し、処罰を受けたり前科がついたりすることはありません。
起訴 or 不起訴はどのような流れできるのか?
刑事事件の登場人物を登場順に並べると、警察、検察、裁判所です。
刑事事件では、まず警察が捜査を行い、捜査が終わると検察官に事件を送致します。これを「送検」といいます。
事件の送致を受けた検察官は、追加で捜査を行い、最終的に「起訴か不起訴か」を判断します。
そして、検察官が起訴と判断した場合、今度は裁判所で「有罪か無罪か。有罪の場合はどのような刑罰にするか」が審理されます。
他方、検察官が不起訴と判断した場合、事件はそこで終結し、裁判所で審理が開かれることはありません。
このように、起訴か不起訴かを判断するのは、警察や裁判所ではなく、検察官です。
日本の法律では、(検察審査会などの一部例外を除いて)検察官のみが起訴か不起訴かを判断する決定権を有しています。
不起訴の種類は?
不起訴にはおおまかに分けて「嫌疑不十分による不起訴」と「起訴猶予」2種類あります。
「嫌疑不十分による不起訴」
「嫌疑不十分による不起訴」とは、証拠が十分ではなく、被疑者が犯罪を行なったことを十分に証明することができないために不起訴とされる場合です。犯罪事実を争っている場合は、嫌疑不十分による不起訴を目指していくことになります。
「起訴猶予」
「起訴猶予」とは、被疑者が犯罪を行ったことは明らかであるものの、情状面(犯罪の内容・軽重、本人の反省状況、被害者の処罰感情など)を考慮して、検察官が不起訴と判断する場合です。犯罪事実について争っていない場合は、起訴猶予を目指していくことになります。
不起訴になると前科はつかない?起訴の場合と不起訴の場合はどう違う?
では、起訴された場合と不起訴になった場合でどのような違いが生じてくるのでしょうか?
先ほども説明したとおり、起訴されると、今度は裁判所で刑事裁判が始まることになります。書面審査だけで終わる略式裁判であれば、裁判所に出頭する必要はありませんが、そうではない正式裁判となった場合は、裁判所に出頭しなければならず、公開の法廷で裁判にかけられることになります。
また、起訴され裁判にかけられることになった場合、裁判所が無罪と判断した場合を除いて、有罪判決を受け、罰金や懲役などの処罰を受けることになります。
そして、有罪判決を受けたという記録は、前科として一生残ることになってしまいます。
したがって、罪を認めている事件の場合、起訴されれば必ず有罪判決を受け、前科がつくことになってしまいます。
他方、不起訴になった場合は、そこで事件は終了し、裁判にかけられることはありません。
当然、有罪判決を受けることもありませんし、処罰もされません。ですから、前科がつくこともありません。
このように、起訴になるか不起訴になるかは、極めて大きな差があります。
不起訴になるためには?弁護士に依頼するメリット
では、不起訴になるためにはどうすればいいのでしょうか?以下では、罪を認めている場合と、認めていない場合に分けて解説します。
罪を認めている場合(自白事件)
まず、罪を認めている場合です。罪を認めている場合は、先ほど説明した起訴猶予を目指していくことになります。
では、検察官はどのような場合に起訴猶予にするのでしょうか?
刑事訴訟法では、以下のように定められています。
第二百四十八条
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
ここで、「公訴を提起しない」とは、「起訴しない(起訴猶予にする)」という意味です。すなわち、検察官は、この条文に書かれているような事情を考慮して、「起訴する必要がない」と判断した場合は、起訴猶予にすることができるのです(これを起訴便宜主義といいます)。
したがって、これらの事情のうち、本人にとって有利になる事柄を検察官に説明し、不起訴にしてもらうよう説得する弁護活動が必要になります。
そして、条文に書かれた事情のうち「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状」は基本的に変えることができませんが、「犯罪後の情況」については、適切な弁護活動を行うことで、事後的に有利な事情を獲得することができます。
「犯罪後の情況」として挙げられるものは、①示談が成立しているかどうか(示談の成否)、②罪を認めてきちんと反省しているかどうか(反省状況)、③再犯の可能性がないかどうか(再犯可能性の有無)などです。
このうち、最も重要なのは、①示談の成否です。検察官は、被害者の処罰感情というものを非常に重く見ます。ですので、被害者と示談が成立し、被害者が罪を許している場合は、こちら側に極めて有利な事情になります。軽微な犯罪であれば、示談をしていれば不起訴になる可能性が非常に高いです。
また、②反省状況も重要であり、きちんと罪を反省していることを検察官に伝える必要があります。具体的には、罪を認めて捜査に協力すること、自分の行いの何が悪かったのかを理解して内省を深めること、被害者にきちんと謝罪をすることなどです。
なお、場合によっては、贖罪寄付といって、罪滅ぼしのために慈善団体などに寄付をし、その証明を検察官に提出することもあります。贖罪寄付は、一般的には弁護士会を通して行うことが多いです。
さらに、③再犯可能性の有無も検察官は重視します。例えば、万引きや盗撮、薬物犯罪を繰り返してしまっているような場合は、精神科や心療内科に通って精神面の治療をすること、交通事故の場合に免許を返納するなど再犯を犯せないような状況を作り出すこと、家族など適切な人に監督者になってもらい嘆願書や誓約書を書いてもらうことなどです。
このように、罪を認めている場合に不起訴になるためには、被害者と示談をするなどして有利な事情を収集した上で、検察官に意見書を提出するなどして不起訴にしてもらうよう説得することが重要です。不起訴の獲得を目指すのであれば、早期に弁護士に依頼することをお勧めします。
罪を認めていない場合(否認事件)
次に、罪を認めていない場合です。罪を認めていない場合は、「嫌疑不十分による不起訴」を目指していくことになります。
先ほども説明したとおり、嫌疑不十分による不起訴とは、犯罪事実を十分に証明できないような場合です。
ですから、捜査機関が組み立てているストーリーとは別の事実である可能性を示せればよいということになります。犯罪事実を証明する責任は検察側にあるので、こちら側のストーリーを証明する必要まではありません。あくまでその可能性が具体的にあることを示せばよいということになります。
そのためには、こちら側にとって有利な証拠を集めるとともに、取調べにおいてどのような供述をするかを判断し(具体的には、黙秘をするのか実際にあった事実を積極的に説明していくのか)、意見書を提出するなどして検察官が想定しているストーリーとは異なる事実である可能性があること説得的に説明していく活動が必要になります。
特に逮捕、勾留されている事案においては、頻繁に弁護人が接見し、取調べの状況を把握するとともに、取調べにどのように対応すべきかを打ち合わせることが重要です。
経験豊富な弁護士による極めて高度な判断が必要になりますから、否認事件において不起訴処分の獲得を目指す場合も早期に弁護士に依頼すべきでしょう。