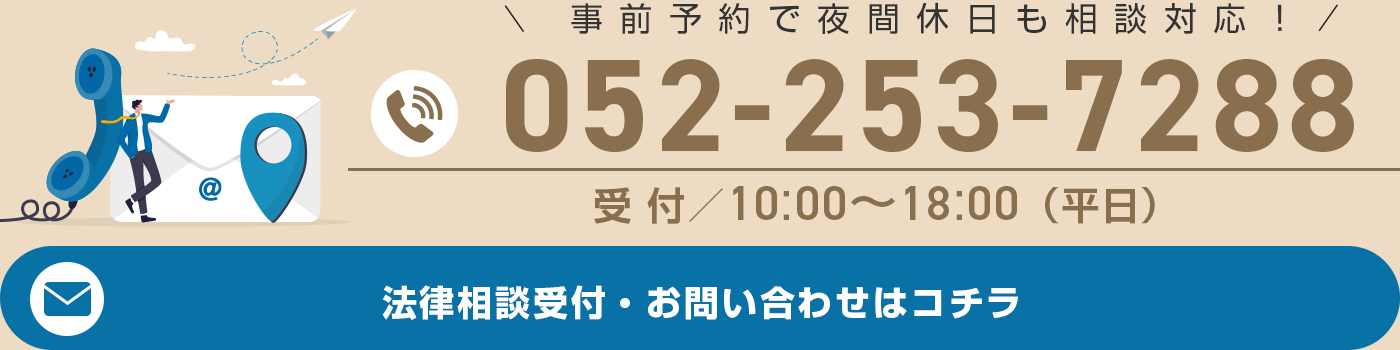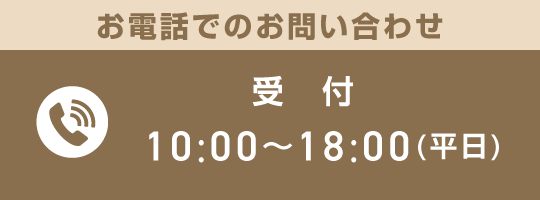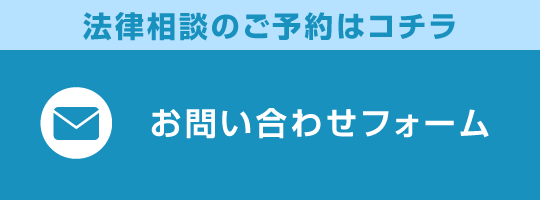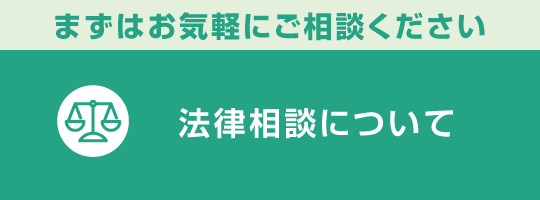このページの目次
Q1 逮捕されるとどれくらいの期間身柄を拘束されるの?
逮捕されると捜査段階で最長23日間身柄を拘束され、その間に検察官は事件を起訴するかどうか判断することになります。
また、起訴(略式起訴は除く)されるとさらに裁判が終わるまで身柄拘束が続くことになります。
もっとも、逮捕後の手続きの中で釈放されるチャンスは何回かあり、弁護人が意見書を出すなどして担当官を適切に説得することで釈放されることもあります。
具体的には、検察官が勾留請求をするかどうか判断する段階や裁判官が勾留するかどうか判断する段階で検察官や裁判官を説得することで、勾留せずに釈放してもらえることがあります。
また、勾留されたとしても準抗告という不服申立てをすることで、勾留の決定が取り消され、釈放される場合があります。
さらに、起訴後も身体拘束が続く場合は保釈請求をすることで身柄を解放してもらえる可能性があります。保釈というのは一定額の保釈保証金を裁判所に預けて身柄を解放してもらうという手続きです(いわば、保釈保証金を人質代わりに裁判所に預けて身柄を解放してもらうというものであり、保釈条件を守っていれば裁判の終了後に返還されます)。
なお、逮捕後の流れについては、以下の関連記事で詳細に解説しておりますので、そちらもご参照ください。
関連記事:「逮捕後の流れ」
Q2 刑事事件を起こしたら報道される?
刑事事件を起こしたからとって必ず報道されるというわけではありません。
そもそも、マスコミがその事件の存在を把握しなければ報道される可能性はありません。
もっとも、逮捕された場合は、警察からマスコミに事件の概要と被逮捕者の名前が伝えられることになるので、報道されるリスクは高まります。
盗撮や万引きといった比較的軽微な事件であっても、逮捕された場合は地方紙の社会面などに実名が掲載されてしまうことはあります。
逮捕されていない場合であっても、被疑者が公務員や大企業の役員など社会的に重要な人物である場合、社会的な耳目を集める重大事件である場合などは、警察からマスコミに情報が伝えられ、報道される可能性が高くなるといえるでしょう。
Q3 刑事事件を起こしたら職場に知られる?
刑事事件を起こしたからといって、警察や検察が職場に連絡することは基本的にありません。
もっとも、事件の現場が職場である場合など、事件自体に職場が密接に関連しており、職場への連絡が捜査に不可欠であるといえるような場合は、当然、連絡されることがあります。
Q4 逮捕された場合、職場や学校への連絡はどうすればいい?
逮捕された場合に職場や学校への連絡をどうするかは大変悩ましい問題です。
逮捕後数日で釈放されることもあれば、捜査段階だけで最長23日間身柄を拘束される可能性もあるからです(再逮捕、再勾留によりさらに身柄拘束が長期化することもあります)。
逮捕された事実を職場や学校が知れば当然何らかの処分を下される可能性が高いので、早期釈放の見込みが十分ある場合は拙速に会社や職場に伝えるのは控えた方がよいでしょう。
他方、早期釈放の見込みがほとんどない場合は、早めに職場や学校に事実を伝え、今後の対応について協議しておいた方がダメージを最小化できる可能性は高くなるかもしれません。
Q5 逮捕された家族と面会はできる?
逮捕直後はご家族などの面会はできません。より正確にいうと、逮捕されてから勾留されるまでの間(時間にすると逮捕から1〜3日間)は、ご本人と面会できるのは弁護士だけです。
他方、勾留後はご家族など面会が可能になります。
もっとも、勾留の決定と同時に接見禁止処分が付されていることがあります。この場合は、勾留後も面会ができないので、裁判所にご家族等との面会について接見禁止を解除するよう申立てる必要があります。
Q6 逮捕されている本人と面会するにはどうすればいい?
ご家族などが逮捕されているご本人と面会する場合は、あらかじめ留置施設(警察署の留置場など)に電話で面会の予約をとっておく必要があります。
当日の予約は受け付けてくれない警察署もあるので、前日のうちに予約をとっておく方が無難でしょう。
面会に伺う際は、本人確認のための身分証と認め印を持参してください。
面会ができるのは平日の日中のみであり、時間は8時30分頃〜16時頃であることが多いですが、受付時間は留置施設によって異なるので、事前に確認をしていた方がよいです。
また、面会できる時間は1回につき15分程度であり、面会時は留置施設の職員が立ち会います。
Q7 差し入れに制限はあるの?
酒やタバコの差し入れはできません。
ボールペンなどのように先の尖ったものも差し入れは不可です。
衣服については、長い紐がついているもの、中にゴムが入っているものなどは基本的に差し入れできません。
小説、漫画などの書籍も差し入れ可能ですが、わいせつな表現が含まれているものは差し入れられません。
メガネの差し入れは可能ですが、コンタクトレンズなどは新品のものでなければなりません。
薬の差し入れはできません。留置施設側に同じ薬を用意してもらう必要があります。
金銭は上限3万円までとされていることが多いです。
なお、留置施設によっても対応が異なることが多いので、正確なところは差し入れ前に留置施設にお問い合わせください。
Q8 本人以外でも弁護人は選任できる
本人以外でも弁護人の選任は可能です。
ご本人から独立して弁護人を選任できるのは配偶者、直系親族、兄弟姉妹などに限りますが、友人や恋人であっても弁護士に依頼することはもちろん可能です。
後者の場合は、まず弁護士が接見などによりご本人の意向を確認してからご依頼いただくことになるでしょう。
Q9 示談はすべき?
被害者のいる事件であれば示談をするメリットは非常に大きいといえます。
検察官や裁判官は、事件について被害弁償をしているか否か、また、被害者が事件についてどう思っているか(被害感情、処罰感情)を非常に重要視します。
示談をすることで適切に被害弁償を行い、被害者から許しを得ていることは、検察官が起訴か不起訴を決めたり、裁判官が量刑を決める上で大きな影響を与えることができます。
Q10 示談ができない場合、贖罪寄付をすべき?
示談ができない場合の次善の策として贖罪寄付が挙げられることがよくあります。
贖罪寄付というのは、罪滅ぼしの意味を込めて犯罪被害者の保護などに努める慈善団体に寄付をすることです。
実際の手続きとしては、弁護人が代理して弁護士会をとおして寄付することが多いです。
金額は事案にもよりますが、比較的軽微な事件だと10万円前後とすることが通常です。
もっとも、贖罪寄付は反省の態度を示す一つの資料にはなるものの、検察官の処分や裁判官の量刑判断に与える影響はそこまで大きくありません。
「起訴か不起訴か」「実刑や執行猶予か」で綱引きをしており「少しでも有利な事情を集めるためにできることは何でもやっておきたい」という場合であれば贖罪寄付も検討すべきですが、そうでない場合は贖罪寄付をするメリットと金銭負担の大きさを比較して判断されることをお勧めします。
なお、青少年保護育成条例違反の場合に限っていえば、贖罪寄付をしたことで不起訴になっている案件も複数あるので、この場合は贖罪寄付をすることを積極的に検討すべきでしょう。
Q11 起訴されると裁判所に行かないといけないの?
起訴には、正式起訴(公判請求)と略式起訴の2種類があります。
正式起訴の場合は、裁判所に出頭し公開の法廷で審判を受けることになります。
他方、略式起訴は簡易裁判所の裁判官が書面作成だけで判断するので、裁判所に出頭する必要はありません。
Q12 起訴されると刑務所にいくの?
起訴されたとしても、無罪判決になった場合は、当然刑務所に行くことはありません。
また、有罪判決であっても罰金刑の場合や刑の全部に執行猶予がつけられた場合は刑務所に入れられることはありません。
他方、(一部執行猶予を含む)実刑判決の場合は、刑務所に収監されることになります。
Q13 略式裁判って何?
検察官が事件を起訴する場合、正式起訴にするか略式起訴にするかを判断します。
正式起訴の場合は、文字通り、公開の法廷で正式な裁判を行うことになります。皆さんが刑事ドラマなどでよく見る普通の刑事裁判を行うということです。
他方、罰金が相当な軽微な事件の場合は、正式起訴ではなく略式起訴になることがあります。
略式起訴の場合、簡易裁判所の裁判官が自分の机の上で書面だけ読んで最終的な判断を下すので、被告人が裁判所に出頭する必要はありません。
また、略式起訴の場合は、必ず100万円以下の罰金になるので、懲役刑を科されることはありません。
判決の内容は後日手紙で略式決定謄本という形で自宅に届きます。その後、検察庁から納付書が届くのでこれにしたがって罰金を納めます。
なお、自宅にこれらの郵便物が届くことを避けたい場合は、事前に伝えておけば、ご自身で取りにいくことも可能です。
Q14 罰金を納めないとどうなるの?
罰金を納めないと労役場というところに留置され、強制的に労働させられることになります。
1日あたりの労働が5000円に換算され、罰金額を完済するまでは労役場から出ることはできません。
なお、労役場というのは、強制的に労働させられる国の施設のことですが、基本的には刑務所と同じ場所にあります。
Q15 捜査機関に押収されたものはいつ返ってくるの?
スマートフォンなどの生活に必要な物品を証拠品として押収されてしまった場合、いつ捜査機関から返してもらえるのでしょうか?
刑事訴訟法には「留置の必要がないもの」は還付しなければならないと定められています。
したがって、捜査に必要がなくなれば返してもらえることになるのですが、いつ「捜査に必要がなくなる」のかは事件の内容や捜査の進捗状況などによってさまざまです。
したがって、「いつまでに」という明確な時期をお伝えするのは難しいところですが、起訴不起訴の終局処分が出れば、返してもらえる可能性は高いです。その場合は、押収されてから数ヶ月程度は返ってこないことになります。
もっとも、スマートフォンなどであれば、捜査機関において解析が終われば、交渉次第ですぐに返してもらえることも多いです。
実際、早期に返却するよう捜査機関を説得したところ、押収されてから数日で返してもらえたこともこれまでたくさんあります。
Q16 裁判所に出頭するときはどんな服装で行けばいいの?
服装や髪型によって判決の内容が変わることはないといわれていますが、裁判官も人間ですから、外見の印象で結論が左右されないという絶対の保証はないでしょう。
したがって、派手すぎたりラフすぎたりする格好は避けるべきといえます。
常識的な格好であれば必ずしもフォーマルウェアである必要まではありませんが、迷ったらスーツで行くのが無難であると思われます。