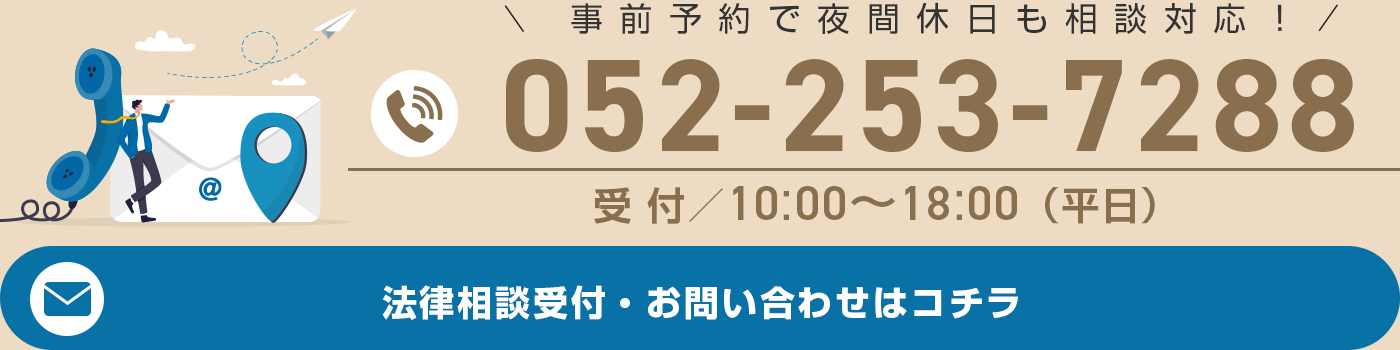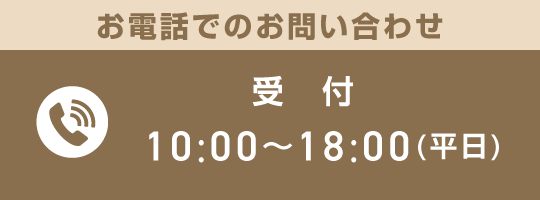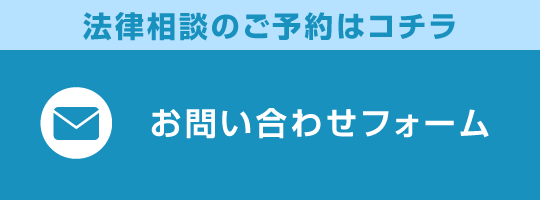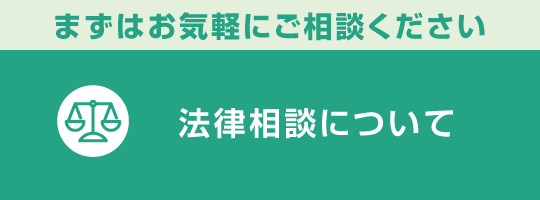このページの目次
遺留分権利者について弁護士が解説します
民法には遺留分という制度があり、被相続人による遺贈や贈与によってこの遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求が可能であるとされています。
では、この遺留分侵害額請求をできるのは被相続人の親族のうちの誰でしょうか?ここでは、遺留分権利者の範囲について解説していきたいと思います。
そもそも遺留分とは?
そもそも遺留分とは何であり、どのような目的で定められた制度なのでしょうか?「遺留分」という言葉は聞いたことがあっても、このことについて正確に理解されている方はあまり多くないかもしれません。
人は自分の財産をどのように扱うかを自由に決めることができます。当然自分で持ち続けてもよいですし、誰かに売ったり、タダであげたりするのも自由です。これを私的自治の原則などといいます。
私的自治の原則は、遺言書を作成する場面についても当てはまります。つまり、自分の財産を自分が死亡した後で誰にどのように引き継がせるかは遺言者が自由に決定することができるのです。したがって、遺産を均等に分け与えてもいいですし、特定の誰かに全財産を集中させるといったこともできます。このことを遺言自由の原則などといったりします。
しかし、遺言自由の原則を徹底すると、本来相続によって遺産をもらえたはずの人が遺産をもらえなかったりして不公平な事態になるおそれがあります。
そして、このことは被相続人が死亡する前に財産を処分していた場合も当てはまります。例えば亡くなる1か月前に全財産を誰かに贈与していたため、相続人が遺産を全く取得できなかったという場合も上記と同様に不公平といえるでしょう。
そこで、被相続人による自由な財産の処分を認めつつ、これによっても奪うことのできない最低限の持分を相続人に保障することで不公平を是正しようというのが遺留分制度の目的なのです。
遺留分権利者の範囲
では、遺留分を請求できる人、つまり遺留分権利者にあたるのは被相続人の親族のうちの誰でしょうか?
民法では「兄弟姉妹以外の相続人」が遺留分を請求できると定められています。
したがってまず、① 兄弟姉妹はたとえ相続人であったとしても遺留分を請求できないということになります。
その理由ですが、自分の兄弟姉妹の遺産に対する相続の期待度は、子どもや親の場合と比べてあまり高くないため、被相続人の財産処分の自由を優先させたからといえるでしょう。
他方、② 兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が保障されていることになります。
もっとも、あくまで「相続人」であることが前提なので、その遺産相続において相続資格を有していない人には遺留分はありません。
したがって、配偶者以外の親族で自分より優先順位の高い親族がいる場合、その人は相続人にはなれないため、遺留分の請求もできません。例えば被相続人に子どもがいる場合、被相続人の親や兄弟姉妹は、相続権がなく、遺留分権者にもなれないということです。
また、相続放棄をした場合も初めから相続人ではなかったとみなされるので、この場合も遺留分を請求できません。相続欠格や排除によって相続権を失った場合も同様です。
子の代襲相続人は、被代襲者である子と同じ遺留分を有します。例えば、被相続人Aに妻Wと子Xがおり、Xには更に子Y(=Aの孫)がいたとします。Aよりも先にXが死亡していた場合、民法ではXの子であるYがXの代わりにAを相続することができるとされています。これを代襲相続といい、Xを被代襲者、Yを代襲相続人といいます。この場合、Yは代襲相続人としてXの相続権を有することになるので、Aの相続においては遺留分権利者になります。
遺留分の割合は?
遺産全体に占める遺留分の割合は民法で次のように定められています。
すなわち、父母等の直系尊属のみが相続人の場合は遺産の3分の1、それ以外の場合は遺産の2分の1が遺留分になります。
遺留分権利者が複数いる場合は、この遺留分割合をそれぞれの法定相続分に従って配分していきます。
例えば、被相続人に妻(法定相続分1/2)と子2人(法定相続分1/4ずつ)がいる場合、妻の遺留分は1/4(=1/2×1/2)、子の遺留分はそれぞれ1/8ずつ(=1/2×1/4)となります(以下の表の④にあたります)。
以下に遺留分割合を表にして整理しておきます。
| 配偶者の遺留分 | 血族相続人全体の遺留分(注) | |
| ①配偶者のみが相続人の場合 | 2分の1 | – |
| ②子のみが相続人の場合 | – | 2分の1 |
| ③直系尊属のみが相続人の場合 | – | 3分の1 |
| ④配偶者と子が相続人の場合 | 4分の1 | 4分の1 |
| ⑤配偶者と直系尊属が相続人の場合 | 3分の1 | 6分の1 |
| ⑥配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 | 2分の1 | なし |
(注)血族相続人とは配偶者以外の相続人のことをいいます。同順位の血族相続人が複数いる場合は、頭数で割ります。