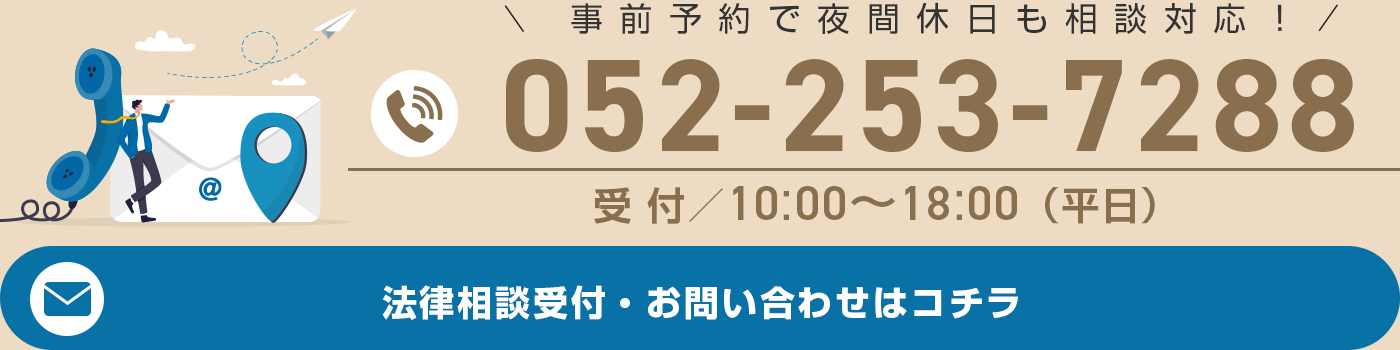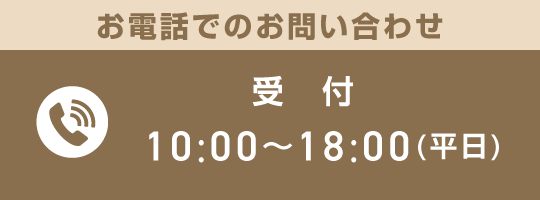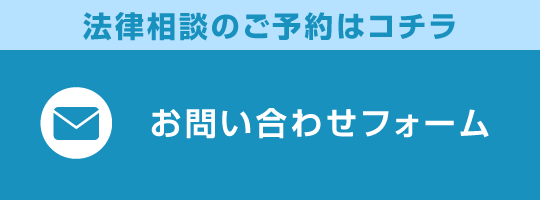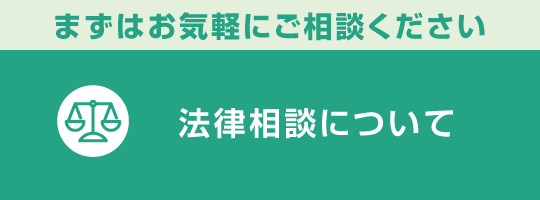遺言書を作成する際に頭を悩ませるポイントの一つが遺留分をどう扱うかです。
遺言書と遺留分をめぐっては実にさまざまなニーズがあります。
例えば、「遺留分をめぐって家族が揉めないように遺留分を侵害しない遺言書にしたい」という人もいれば、「遺留分を侵害してでも特定の相続人に遺産を集中させたい」という人もいらっしゃいます。
また、「遺留分ができるだけ少なくなるように対策しておきたい」という要望もよく聞きます。
ここではそのようなさまざまな要望に応えるべく、遺言書における遺留分の取り扱いや遺留分対策について解説していきたいと思います。
このページの目次
遺留分と遺留分割合
遺留分とは?
遺留分というのは、相続人に保障された最低限の取り分のことです。
人は遺言によって自由に財産を処分することができ、例えば、特定の誰か(相続人である必要さえありません)に全財産を与えるといったことも可能です。
しかし、それでは相続によって遺産を取得できたはずの相続人にとって酷な結果となってしまいます。
そこで「遺留分」として、相続人に最低限の取り分を保障しておこうというのが遺留分制度の趣旨です。
具体的には、各相続人に一定割合の遺留分を保障しておき、それに満たない取り分しかもらえなかった相続人は、遺留分を侵害する遺贈や贈与の受遺者(遺贈を受けた人)、受贈者(贈与を受けた人)に対して遺留分侵害額の請求ができるという制度になっています。
遺留分については、その計算方法などについて別の記事でも詳しく解説しておりますので、こちらの関連記事をご参照ください。
関連記事:「遺留分を請求したい人へ」
遺留分の割合
上述のとおり、遺留分というのは、相続人に一定の割合で保障された最低限の取り分のことです。
では、保障されている遺留分の割合はどの程度でしょうか?
まず、民法によると遺留分を保障されているのは「兄弟姉妹以外の相続人」なので、被相続人の兄弟姉妹に遺留分はありません。
兄弟姉妹以外の相続人に保障された遺留分全体の割合は、直系尊属(父母等)のみが相続人の場合は遺産全体の3分の1、それ以外の場合は遺産全体の2分の1です。
遺留分権利者が複数いる場合は、更にこれを法定相続分に従って分け合うことになります。
例えば、被相続人に妻と子2人がいる場合、全体の遺留分は2分の1であり、これを各相続人の法定相続割合(妻:1/2、子:各1/4ずつ)で分け合うことになるので、妻が1/4、子がそれぞれ1/8ずつとなります。
この遺留分割合さえ与えられなかった場合は、「遺留分が侵害された」状態になるというわけです。
遺留分割合を表にして整理すると以下のようになります。
| 配偶者の遺留分 | 血族相続人全体の遺留分(注) | |
| ① 配偶者のみが相続人の場合 | 2分の1 | – |
| ② 子のみが相続人の場合 | – | 2分の1 |
| ③ 直系尊属のみが相続人の場合 | – | 3分の1 |
| ④ 配偶者と子が相続人の場合 | 4分の1 | 4分の1 |
| ⑤ 配偶者と直系尊属が相続人の場合 | 3分の1 | 6分の1 |
| ⑥ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 | 2分の1 | なし |
(注)血族相続人とは配偶者以外の相続人(血のつながった相続人)のことをいいます。同順位の血族相続人が複数いる場合は、頭数で割って計算します。
遺留分を侵害する遺言書も許される?
遺留分を侵害するような遺言書を作成することは許されないとお考えの人も多いですが、これは実は誤った認識です。
遺言書によって遺留分が侵害された場合、侵害された相続人(遺留分権利者)が遺留分侵害額請求をできるようになるというだけであり、遺言書の効力には何ら影響はありません(なお、遺留分侵害額請求をするか否かも遺留分権利者の自由な判断に委ねられているので、必ず遺留分侵害額の清算が必要になるというわけでもありません)。
このように、遺留分を侵害する遺言書を作成することも法的には問題なく許されます。
ですので、事業承継や各相続人との関係性などから「遺留分を侵害してでも特定の人に遺産を集中させたい」という要望がある場合は、そのような遺言書を作成してしまっても構いません。
他方、遺言書によって特定の相続人の遺留分を侵害する場合、遺された人たちが遺留分をめぐって争いになるおそれがあるので、その点はよく考慮して判断すべきといえるでしょう。
また、さまざまな事情によって遺留分を侵害する遺言書となる場合でも、遺留分権利者に遺留分の放棄をしてもらうよう説得する、遺言書の付言事項に遺留分侵害額の請求をしないよう求める旨記載しておくなどして、できるだけ揉めないような対応を講じておくことが望ましいといえるでしょう。
トラブル回避のためには遺留分に配慮した方がいい?
遺留分を侵害する遺言書を残した場合、遺留分をめぐって遺された親族らが激しい争いに発展するおそれがあります。また、そうなると遺言書で多くの遺産を取得した人も、遺留分侵害額請求に対応しなければならず、大きな負担になります。
これでは、せっかく遺言書を残した意義が大幅に低減してしまいます。
遺留分をめぐって親族がトラブルになることを避けたいのであれば、遺留分に配慮し、遺留分を侵害しないような遺言書にした方が無難といえるでしょう。
例えば、事業用資産を後継者相続人に相続させるのであれば、事業用以外の財産を他の相続させるなどして遺留分を侵害しない遺言書にした方がトラブルを回避できる可能性は高まります。
なお、遺留分の計算方法については、以下の関連記事で詳細に解説しておりますので、こちらをご参照ください。
もっとも、遺留分の計算は非常に複雑であり、専門家でないと難しいので、弁護士に相談することをおすすめします。
関連記事:「遺留分を請求したい人へ」
遺留分をできるだけ少なくするためには?
遺留分は法律で認められた権利なので、これを一方的に奪うことはできません。
他方、遺留分を侵害する遺言書とする場合でも、遺留分に配慮する遺言書とする場合でも、できるだけ遺留分が少なくなるようにしたいという要望をお持ちの方は多いと思います。
遺留分侵害額の計算は法律で決まっているのでなかなかに難しいところですが。遺留分をできるだけ少なくするための方策として考えられることを挙げておきます。
① 生命保険を活用する
最高裁の判例(最判平成14年11月5日)によると生命保険金はその受取人の固有の権利なので、相続財産には含まれないとされています。
したがって、Aさんが死亡し、Bさんが生命保険金として3000万円を受け取っても、これは相続財産を受け取ったことにはならないので、原則として、何ら遺留分を侵害していないということになります。
ですので、自分の資産を保険料として保険会社に支払っておき、資産を譲りたい人をその生命保険の受取人に指定しておくことで、遺留分を侵害することなく、資産の移転が可能になります。
この方法によれば、保険金を受け取った人も、原則として、遺留分侵害額請求を受けることはありません。
もっとも、上記の最高裁判例でも、保険金受取人と他の相続人との不公平が著しい場合は、遺留分を侵害する特別受益として扱われる可能性があると指摘しており、この方法が絶対にうまくいくというわけではなさそうです。
② 遺留分を放棄してもらう
例えば、事業承継のために事業用の資産や株式を特定の親族に相続させたい場合、多大な費用をかけてつきっきりで介護をしてくれた親族に多くの遺産を残してあげたい場合など、遺留分の侵害にもさまざまな理由があります。
そこで、遺留分を侵害されてしまう相続人(遺留分権利者)に対して、そのような理由を説明し、遺留分を放棄してもらうことが考えられます。
この方法は、遺留分権利者に任意に遺留分を放棄してもらおうというものなので、遺留分権利者に拒まれた場合に放棄を強制することは当然できません。
また、被相続人の生前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所で許可を受ける必要があります。
③ 経営承継円滑化法に定める特例の適用を受ける
中小企業の代表者が死亡した場合に経営の承継が円滑に進むように、経営承継円滑化法では、遺留分に関する民法の特例を設けており、この特例を受けると、先代経営者からの遺贈、贈与等によって取得した自社株式や事業用資産について、遺留分算定の基礎財産に含めないことなどが可能になります。
もっとも、この制度を利用できる場面が極めて限定的であるとともに、要件もかなり厳しく、手続きも煩雑であるため、ここでは詳しい解説を割愛させていただきます。
詳しく知りたいという方は中小企業庁のホームページをご参照ください。https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu.htm
④ 養子縁組をする
これはウルトラCですが、遺留分権利者が子である場合、子の数が増えると当然一人当たりの遺留分額も減るので、誰かと養子縁組をして相続人を増やすことで、遺留分侵害額を減らすという方法も理論上は考えられるところです。
もっとも、当然ですが、縁組をした養子にも相続権が発生してしまいますので、実際にそのような方法を採るか否かは慎重にご検討ください。