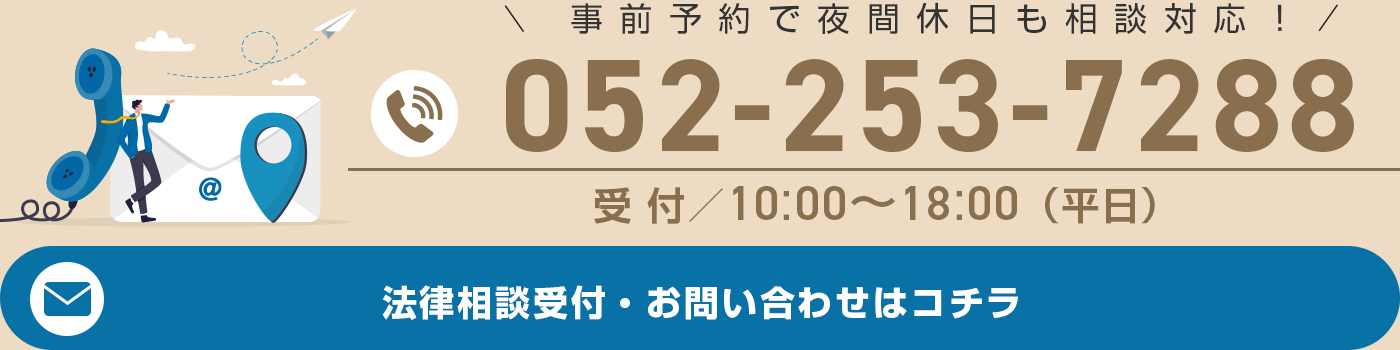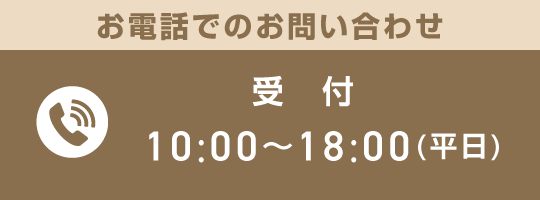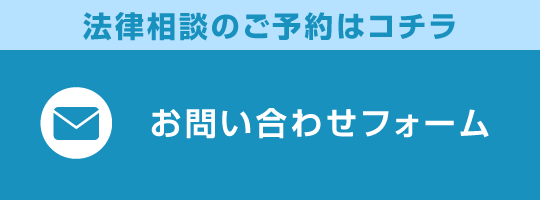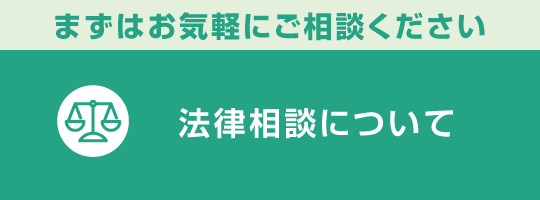このページの目次
遺留分を請求された場合の対処法について弁護士が解説します
ここでは「突然遺留分の請求をされてどうしたらいいのかわからない」という方のために、遺留分を請求された場合の対処法について解説していきたいと思います。
そもそも遺留分って何?
遺留分というのは、いわば相続人に保障された最低限の持分のことです。
人は自分の財産をどのように処分するかを自由に決めることができます。ですので、自分の持っている財産を人に売ったり、タダであげたりするのも自由です。
これは遺言書を作る場合も同様で、自分の財産を自分の死後、誰にどのように分けるのかは遺言者が自由に決めることができます。
しかし、それによって本来遺産をもらえたはずの相続人が全く遺産をもらえなかったり、もらえたとしてもほんのわずかしかなかったりした場合、その相続人にとって不公平ではないかと民法を作った人たちは考えました。
そこで、自由に自分の財産を処分できることは前提としつつも、相続人の最低限の持分として遺留分を保障することで、不公平を緩和しようとするのが遺留分制度の趣旨です。
具体的には、遺留分として保障された持分を遺贈や贈与などによって侵害された場合、その侵害された人が受遺者(遺贈を受けた人)や受贈者(贈与を受けた人)などの遺留分侵害者に対して、侵害された遺留分額(遺留分侵害額)の支払いを請求できるという制度になっています。
遺留分侵害額の請求を受けたらすべき5つのこと
遺留分侵害額を請求されたからといって、直ちにそれに応じなければならないわけではありません。遺留分を請求された場合は、以下のことをすべきでしょう。
① 請求者が遺留分権利者かどうか確認する
まず、遺留分を請求してきている人が本当に遺留分を請求できる人(遺留分権利者)であるかどうかを確認すべきでしょう。
民法で遺留分権利者は「兄弟姉妹以外の相続人」と定められています。
したがって、まず被相続人の兄弟姉妹は遺留分権利者になれません。
また、兄弟姉妹以外の親族であっても、その相続において相続権を有していない人は遺留分権利者になれません。
その相続において相続権を有していない人とは、より優先順位の高い親族がいる場合の後順位の親族(被相続人の子がいる場合の直系尊属(父母等)、直系尊属がいる場合の兄弟姉妹)のことや、相続放棄をした親族などのことをいいます。
遺留分権利者の範囲については、次の関連記事で詳しく説明しておりますので、そちらも参考にしてください。
関連記事:「遺留分を請求できる人の範囲は?」
② 請求されている金額が妥当かどうかを確認する
請求されている遺留分侵害額が適切かどうかも確認しておくべきでしょう。
以下で遺留分侵害額の計算方法を解説しますが、その内容は極めて複雑であるため、専門家でないと正確な金額の算定は難しいと思われます。
【相手方の遺留分額】の計算
遺留分侵害額を計算するためには、まず【相手方の遺留分額】を求めます。計算式は以下のとおりです。
【相手方の遺留分額】=【基礎となる財産】 × 【個別的遺留分割合】
【基礎となる財産】=【被相続人が相続開始時点で有していたプラスの財産(注1、2)】+【贈与された財産(注3)】−【相続債務の全額】
(注1)遺贈は無視して計算します。例えば1億円の遺産があり、そのうちから5000 万円の遺贈がされていたとしても、相続開始時点のプラスの財産は1億円として計算します。
(注2)不動産など価格が増減する資産については、相続開始時点の評価額が基準となります。
(注3)【贈与された財産】は、原則として、相続開始前1年以内にされた贈与に限ります。
ただし、遺留分権利者に損害を与えることを知りながらされた贈与であれば、1年よりも前にされた贈与も含めて計算します。
また、相続人に対する特別受益としてなされた贈与(婚姻、養子縁組のため又は生計の資本としてされた贈与)は、相続開始前10年以内にされたものであれば、贈与として基礎財産に加算されます。
【個別的遺留分割合】=【総体的遺留分割合(注1)】 ×【相手方の法定相続分(注2)】
(注1)総体的遺留分割合は民法で決まっており、直系尊属(≒被相続人の父母など)のみが相続人の場合は遺産全体の3分の1が、直系尊属以外の相続人もいる場合は遺産全体の2分の1が遺留分になります。
(注2)遺留分権利者が複数いる場合は、相対的遺留分割合にその者の法定相続分をかけて個別的遺留分割合を計算します。配偶者と子2人がいる場合、配偶者の個別的遺留分割合は1/4(=1/2×1/2)、子らの個別的遺留分割合はそれぞれ1/8(=1/2×1/4)ずつになります。
遺留分侵害額の計算式
【相手方の遺留分額】が計算できたら、以下の式に従って、遺留分侵害額を計算します。
遺留分侵害額=【相手方の遺留分額】−【相手方が受けた遺贈及び特別受益である贈与の金額(注)】−【相手方がその相続において取得した遺産の額】+【相手方が負担する相続債務の金額】
(注)特別受益である贈与とは、婚姻、養子縁組のため又は生計の資本としてされた贈与のことをいいます
以下に計算の具体例を示しておきます。
【具体例】
Aには妻Wと子X、Yがいました。Aは「遺産の中から4000万円をBに、300万円をWに、200万円をXに与える」という遺言を残して死亡しました。
Aの死亡時の財産総額は4500万円でした。
また、Aは死亡時、800万円の借金を負っていました。
さらに、Aは死亡する半年前に生計維持のために1500万円をYに贈与していました。
BがW、X、Yから遺留分侵害額請求を受けたとき、支払わなければならない金額はいくらになるでしょうか?

W 、X、 Y遺留分額は以下のように計算されます。
W:(4500万円+1500万円−800万円)×1/2×1/2=1300万円
X:(4500万円+1500万円−800万円)×1/2×1/4=650万円
Y:(4500万円+1500万円−800万円)×1/2×1/4=650万円
W:0円
X:0円
Y:1500万円
遺言の内容から、以下のようになります。
W:300万円
X:200万円
Y:0円
相続債務800万円を法定相続分に従って負担することになるので、以下のようになります。
W:800万円×1/2=400万円
X:800万円×1/4=200万円
Y:800万円×1/4=200万円
以上から遺留分侵害額は以下のようになります。
W:1300万円−300万円+400万円=1400万円
X:650万円−200万円+200万円=650万円
Y:650万円−1500万円+200万円=−650万円→0円
③ 自分が本当に遺留分義務者であるか確認する
遺贈や贈与を受けた遺留分侵害者が複数いる場合、民法では誰に対して遺留分侵害額を請求すべきかについて、以下のようなルールを定めています。
ⅰ 受遺者と受贈者がいる場合 → 受遺者に先に請求する。
ⅱ 受遺者が複数いるとき、または受贈者が複数いる場合においてその贈与が同時にされたものであるとき → 受遺者または受贈者にその目的物の価額に応じて請求する。
ⅲ 異なる時期にされた贈与の受贈者が複数いるとき → 後の贈与の受贈者から順に請求する。
ですので、例えばあなたが「被相続人から生前贈与を受けていた」として遺留分侵害額の請求を受けている場合、他に遺贈を受けている人(受遺者)がいれば先にそちらに請求するよう相手方に求めることができるということです。
④ 時効が成立していないか確認する
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分侵害の事実を知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅するとされています(民法1048条前段)。
このように遺留分侵害額請求については、1年間という短い時効期間が設けられているため、請求を受けた場合は、この期間が過ぎていないかどうかも確認すべきでしょう。
なお、相続開始のときから10年が経過したときは、遺留分権利者が相続開始の事実や遺留分侵害の事実を知っているか否かにかかわらず、遺留分侵害額請求権は消滅するとされています(民法1048条後段)。
⑤ 手元に現金が用意できない場合は裁判所に猶予期限の許与を申立てる
遺留分侵害額を請求された場合に、すぐに金銭を準備することができず、不利益を被ることも考えられます。
そこで、民法では、遺留分侵害額請求を受けた受遺者や受贈者の請求により、裁判所が、金銭債務の全部または一部について相当の猶予期限を許与することができると定められています(民法1047条5項)。
裁判所から猶予期間を与えられた場合、その期間内は支払いをしなくても履行遅滞にならず、遅延損害金の支払義務なども発生しません。
手元にすぐに現金が用意できない場合は、この制度の利用も検討すべきでしょう。
遺留分を請求された場合の流れ
遺留分の請求は、通常、任意交渉から始まります。
任意交渉で双方合意ができれば、そこで終了しますが、合意ができない場合は家庭裁判所で調停が開かれます。
調停でもお互いに合意ができないと、今度は訴訟が提起され、裁判所が遺留分侵害額について判断することになります。
遺留分を請求されたらすぐに弁護士にご相談を
遺留分侵害額請求を受けた場合に一番やってはいけないことは、請求を無視することです。請求を無視していると、調停や訴訟を起こされてより面倒なことになりかねません。
遺留分侵害額請求を受けた場合は、速やかに弁護士が間に入って、請求の妥当性を判断した上で、相手方と交渉をしていくのがよいでしょう。
請求を受けた方はぜひお気軽にご相談ください。