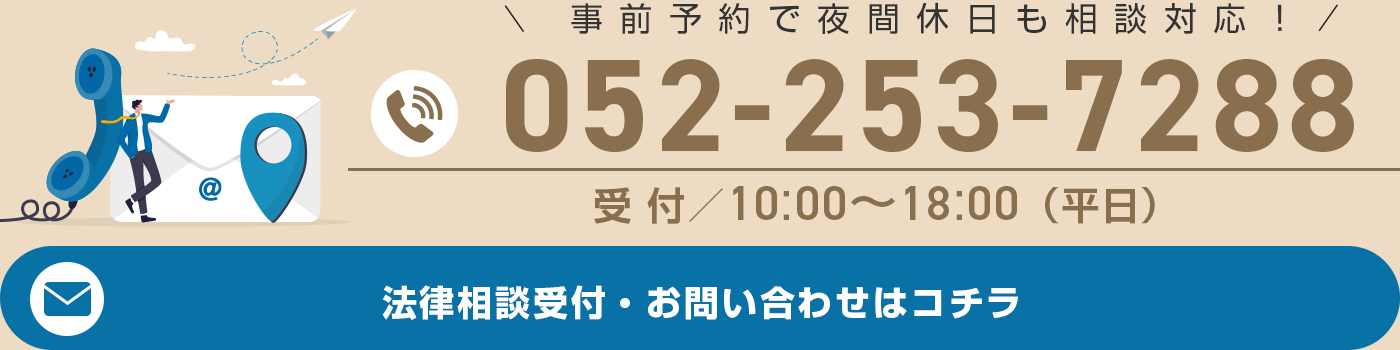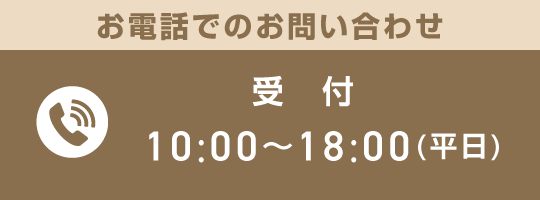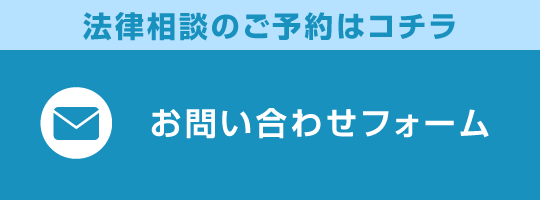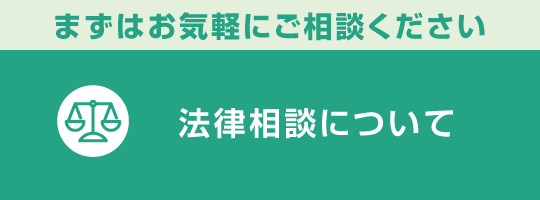このページの目次
相続人調査(戸籍調査)の方法について弁護士が解説します
親族が亡くなり、遺産分けをする場合、相続人の調査が不可欠です。そこで、このコラムでは相続人の調べ方について弁護士が解説していきます。
相続人調査の必要性
遺産分割を行う前提として、相続人の調査は必ず行う必要があります。その理由は二つあります。
まず第1に、遺産分割協議をした後で他の相続人の存在が明らかになった場合、遺産分割協議が無効になってしまいます。血みどろの(?)相続争いの末にようやく遺産分割協議がまとまったのに、後で無効になってしまっては元も子もありません。
第2に、相続人調査を行わずに遺産分割協議書を作成しても、預金の払戻しや不動産の移転登記ができません。
遺産分割協議書に基づいて預金の払戻しや不動産の移転登記をする場合、他に相続人が存在しないことを示す資料(被相続人の出生から死亡までの戸籍又は法務局で認証を得た法定相続情報一覧図)の提出が求められます。
相続人調査を経ていないと、この資料を提出することができませんので、せっかく遺産分割協議書を作成しても、肝心の資産の移転を実行することができなくなってしまいます。
以上のことから、相続人調査は相続手続きにおいて必ず行わなければなりません。
相続人になるのは誰?
相続人調査をする上で、そもそも誰が相続人になるのかを知っておく必要があるでしょう。
誰が相続人になるかは、民法で以下のように定められています。
配偶者
必ず相続人になる
配偶者以外の相続人(血族相続人)
①子、②直系尊属(被相続人の両親など)、③兄弟姉妹の優先順位で相続人になる(先順位の親族がいる場合、後順位の親族は相続人になれない)
例えば、被相続人であるAに妻W、子X、Y、親Zがいる場合、相続人になるのは妻Wと子X、Yであり、Zは相続人になれません。
なお、被相続人が死亡する前に、相続人になりうる人(ただし、直系尊属は除きます)が死亡していた場合は、その子が相続人になることができます。これを代襲相続といいます。
例えば、Aに妻Wと子X、Yがいたとします。Xには子Z(つまりAの孫)がいました。Aが死亡する前にXが死亡していた場合、Aの相続においてはZも相続人(代襲相続人)になることができます。
相続人の調べ方
出生から死亡までの戸籍が必要
相続人を調べるためには、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を収集する必要があります。
「亡くなった時点の戸籍だけを見ればいいのではないか?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、結婚や転籍、戸籍の改製によって新戸籍を編成した場合、それまでに死亡や結婚などによって戸籍から除かれた人の記載は新戸籍には引き継がれません。
したがって、出生戸籍まで遡らないと、相続人を漏らしてしまう可能性があります。
出生から死亡までの戸籍の収集方法
まずは、被相続人死亡時の本籍地で、被相続人が死亡した旨の記載のある戸籍を取り寄せるところから始めます。そして、ここから一つずつ戸籍を遡っていくわけです。
死亡時の戸籍を取り寄せたら、その戸籍の身分事項欄に従前戸籍に関する記載(婚姻や養子縁組など)があるかないかを確認します。
記載がある場合、「身分事項に記載がある入籍日」と「戸籍が編成された日」(身分事項欄に記載があります)を比較し、被相続人の入籍日と従前本籍地を確認します。
戸籍編成日が身分事項記載の入籍日よりも後の場合、入籍日は戸籍が編成された日になり、同一の本籍地に改製前の戸籍(改製原戸籍)があることになります。
逆に、戸籍編成日が身分事項記載の入籍日よりも前の場合、入籍日は身分事項記載の入籍日であり、従前本籍地(当該身分事項に記載されています)に一つ前の戸籍があることになります。
このように一つ前の戸籍を突き止めたら、今度はその戸籍の記載を手がかりにさらに一つ前の戸籍を突き止めます。例えば、「X県Y市より転籍届出昭和○年○月○日受付入籍」と記載があれば、Y市が一つ前の本籍地であることが考えられるので、Y市から戸籍を取り寄せます(「入籍」に関する記載が複数ある場合は、最新のものがその戸籍に入籍日であると考えます)。
なお、戸籍を遡った際は、必ず二つの戸籍が連続しているかどうかを確認する必要があります。具体的には、前の戸籍の「除籍日」と後の戸籍の「入籍日」が一致しているか否かを確認し、一致している場合は二つの戸籍が連続していることが確かめられます。
このように一つずつ戸籍を遡っていって、出生時の戸籍まで辿り着けばようやく出生から死亡までの戸籍が揃ったことになります。
出生から死亡までの戸籍が揃ったら次は何をすべきか?
① 配偶者の有無の確認
被相続人の出生から死亡までの戸籍から、配偶者の有無を確認します。
それにより、被相続人の婚姻歴が判明したような場合は、その配偶者の現在までの戸籍を取り寄せ相続開始時点での生存の有無を確認します。
② 子の有無の確認
また、子の存在が判明した場合は、その子の現在までの戸籍謄本を取り寄せ、相続開始時点での生存の有無を確かめます。
その子が被相続人の死亡前に死亡していた場合は、代襲相続の可能性がありますので、戸籍により相続開始時点における孫やひ孫の存在を確認する必要があります。
③ 子がいなかった場合(直系尊属の確認)
子の存在が確認できなかった場合は、生存している直系尊属(父母等)の現在までの戸籍を取り寄せ、直系尊属の存在を確認します。
④ 直系尊属が全員死亡していた場合(兄弟姉妹の確認)
直系尊属が全員死亡していた場合は、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、兄弟姉妹の存在を確認します。兄弟姉妹の存在が確認できた場合は、現在までの戸籍を取り寄せ、生存の有無を確認します。
兄弟姉妹が被相続人の死亡前に死亡していた場合は、代襲相続の可能性があるので、戸籍により、相続開始時点における甥や姪(代襲相続人)の存在を確かめる必要があります。
相続人調査は弁護士に依頼を
ここまで、相続人調査の方法について説明してきましたが、とても複雑で面倒な手続きであることはお読みになればお分かりいただけたかと思います。
また、高度な専門的知識が必要であるとともに、相続人調査は相続手続きの根幹なので間違いも許されません。
そのような相続人調査をご自身でされることは大きなコストであるとともに、相続人を遺漏してしまうリスクもあり、あまりおすすめできません。
相続人調査はプロである弁護士に依頼されることをおすすめします。
名古屋H&Y法律事務所では、5万円〜で相続人調査をお受けしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。