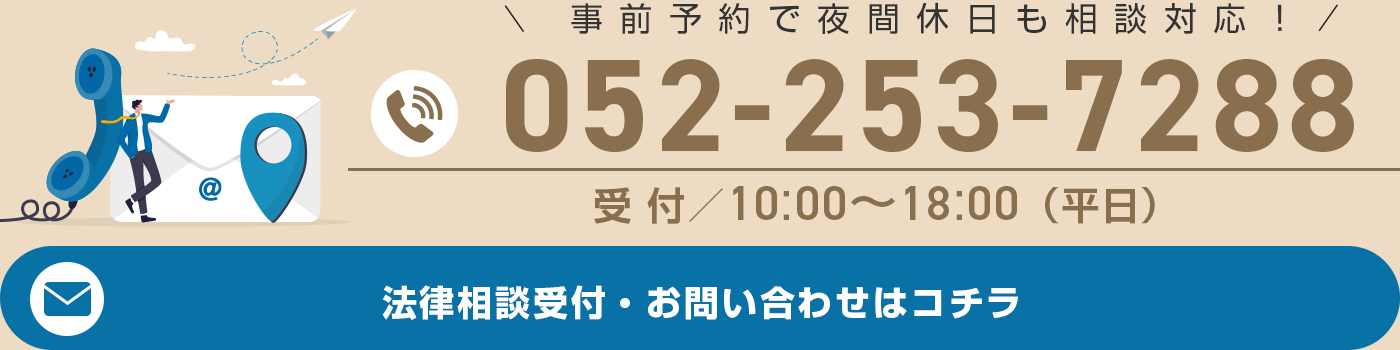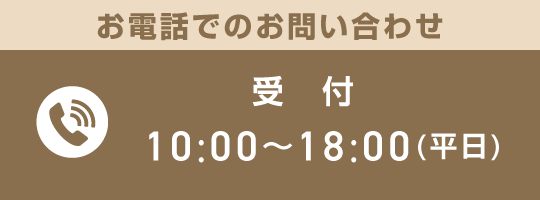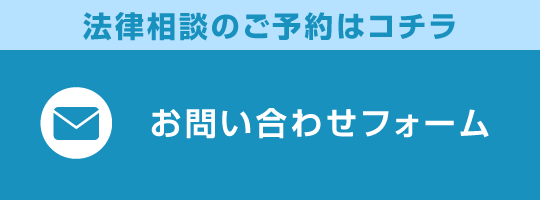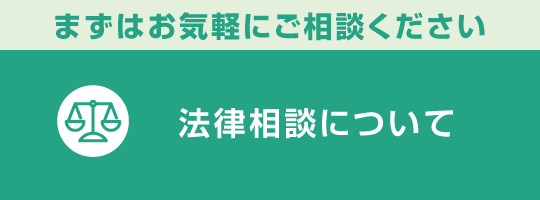このページの目次
遺産相続の流れについて弁護士が解説します
ここでは「身内が亡くなり遺産を相続することになったが相続手続きの流れがわからない」という人たちのために、相続手続きがどのような流れで進んでいくのかついて解説していきたいと思います。
相続手続きの流れ
相続手続きの流れは概ね以下のとおりです(順番は前後したり同時並行になったりすることがあります)。
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 単純承認、相続放棄、限定承認の選択
- 遺言書の有無の調査
- (公正証書遺言又は法務局保管の自筆証書遺言以外の遺言書がある場合)遺言書の検認
- (遺言書がある場合)遺言書の効力と内容の確定
- 遺産分割
- 財産移転の手続き
⑤と⑥は遺言書がない場合は不要です。
それでは、以下で一つずつ見てきましょう。
① 相続人調査
相続手続きを進めていくにあたっては、大前提として誰が相続人になるのかを確定されていなければなりません。そこで、相続手続きにおいては、相続人の調査が必須となります。相続人調査を行わずに遺産分割をしても預金の払戻しや不動産登記ができません。
相続人調査の詳細については、次の関連記事で詳しく解説しておりますので、そちらをご覧ください
関連記事:「相続人はどうやって調べればいい?」

② 相続財産調査
相続手続きを進めていくためには、相続人に加えて遺産としてどのような種類の財産がどれくらいあるのかを確定する必要もあります。そこで、相続人の調査だけでなく、相続財産調査も必要です。
相続財産調査の詳細については、次の関連記事で詳しく解説していますので、そちらをご覧ください。
関連記事:「相続財産の調査はどのようにすればよいか?」

③ 単純承認、相続放棄、限定承認の選択
相続人は、相続開始を知ったときから3か月以内に、単純承認、相続放棄、限定承認を選択しなければなりません。
何も選択せずに3か月が経過した場合は、単純承認をしたものとみなされます。
単純承認をすると、被相続人のすべての権利と義務を相続分に応じて相続することになります。
他方、相続放棄とは、文字どおり、相続人としての地位を放棄することです。相続放棄をした場合は初めから相続人でなかったものとみなされます。
被相続人が多額の借金を背負っていた場合など、マイナスの遺産の方がプラスの遺産よりも多い場合は相続放棄をすることが多いといえるでしょう。
なお、相続放棄をするには、家庭裁判所での手続きが必要になります。
限定承認とは、相続によって取得したプラスの財産の限度でマイナスの財産を弁済することを条件に相続を承認することです。たとえプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多かったとしても、足が出た分は弁済する必要がないということです。
こう聞くと非常に使い勝手が良さそうに思われるかもしれませんが、限定承認は共同相続人全員でする必要がある上、手続的な負担が非常に重たいため、ほとんど利用はされていないのが現状です。

④ 遺言の有無の調査
遺言相続と法定相続
相続には大きく分けて遺言相続と法定相続の2つがあり、遺産分割の進め方などがこの2つで大きく異なります。
遺言相続というのは遺言書がある場合の相続のことをいい、法定相続というのは遺言書がない場合の相続のことをいいます。
皆さんもご存知のとおり、人は自分が死亡した場合に、自分の遺産を誰に対してどのように与えるかを決めておくことができ、この遺産の分け方について記した文書のことを遺言書といいます。
遺言書が残されていた場合、基本的にはその遺言書に従って被相続人の遺産を分けることになります。これが遺言相続です。
他方、当然ながら、亡くなる人が全員遺言書を残しているわけではなく、遺言書を作成しないまま亡くなる方もいらっしゃいます(むしろ件数的には遺言書がない場合の方が圧倒的に多いです)。
遺言書がない以上、相続人は法律(民法)に定められた基準にしたがって遺産を分けることになります。これが法定相続です(「法」に「定」められた「相続」というわけですね)。
遺言書の有無はどのように調べる?
では、遺言書があるかないかはどのように調べればよいのでしょうか?
被相続人が生前に遺言書の有無や保管場所について教えてくれていれば問題はありませんが、そうでない場合は相続人が自分で遺言書を探さなければなりません。
遺言書には、ア 自筆証書遺言、イ 秘密証書遺言、ウ 公正証書遺言の3種類があり、遺言書の探し方もそれぞれ異なりますので、以下で順番に解説したいと思います。なお、遺言書がどういった形で残されているかわからない場合は、ア〜ウのすべての調査を行う必要があります。
ア 自筆証書遺言
まず、自筆証書遺言ですが、これは文字通り、遺言者が自分自身で手書きで作成し、署名押印する場合の遺言書のことです(ただし、財産目録の部分は印字でもOKです)。
自筆証書遺言は、遺言者が自分で保管するのが基本ですが、令和2年にできた「自筆証書遺言保管制度」という制度を利用して法務局に保管を委託することも可能です。
後者の場合、遺言者の死後に相続人が法務局に問い合わせることで、自筆証書遺言が保管されていないかどうかを調べることができます。
具体的には、相続人は法務局に対し1通800円で「遺言書保管事実証明書」の交付を請求することができ、これにより法務局に自筆証書遺言が保管されているか否か、保管されている場合にはどこの法務局で保管されているかなどの事実を調べることができます。
どこか1箇所の法務局に請求をすれば全国の法務局での保管の有無を網羅的に調べてくれるのでその点では便利な制度といえるでしょう。
そして、遺言書の保管が確認できた場合は、「遺言書情報証明書」の交付申請をすることができます。遺言書情報証明書には、保管されている遺言書の画像が記載されているので、これにより遺言書の内容を確認することができます。遺言書情報証明書の交付手数料は1通につき1400円です。
他方、法務局で保管されていない場合は被相続人が自分で保管をしている可能性が考えられますから、被相続人の生前の住居や遺品、貸金庫などを実際に探してみるしかありません。
被相続人がせっかく遺言書を作っていたのにそれが見つからずに法定相続になる場合もありうるところですので、生前に遺言書の有無や保管場所などを確認しておくとよいでしょう。
イ 秘密証書遺言
秘密証書遺言は、その内容を遺言者以外の人に秘密にするための制度です(利用件数は少なく、全国でも年間100件程度です)。
具体的にはまず、遺言者が作成し署名押印した遺言書に封をして閉じます。その後、公証役場で公証人や証人がその封筒に署名、押印することで完成します(したがって、公証人も証人も遺言書の内容を知ることはできません)。
これにより、遺言書の内容を秘密にしつつ、遺言書の存在を証明することが可能になります。
秘密証書遺言は、公証人と証人が署名、押印した後、遺言者に返還され、遺言者が自分自身で保管をします。
被相続人が秘密証書遺言を作成したことがあるかどうかは公証役場に問い合わせることで調べることができます。
すなわち、公証役場では遺言検索システムと呼ばれるシステムが導入されており、平成元年以降に全国の公証役場で作成された遺言書に関する記録がデータベース化されています。ですので、最寄りの公証役場に問い合わせれば、全国すべての公証役場で秘密証書遺言が作成されたことがあるかどうかを検索してもらうことができます。なお、検索の申し出は無料です。
もっとも、秘密証書遺言は、上述のとおり、公証人も遺言書の内容を知ることができませんし、作成された遺言書は公証役場で保管されるのではなく、本人が自分で保管をします。
ですので、公証役場に問い合わせても、わかるのは「過去に秘密証書遺言を作成したことがあるかどうか」のみであり、それがどこに保管され、どのような内容のものであるかは分かりません。
したがって、遺言検索システムにより秘密証書遺言が作成された事実が判明したとしても、結局、相続人が被相続人の遺品等から遺言書を探し出さなければなりません。
ウ 公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場において公正証書として作成される遺言書のことであり、作成後は公証役場で原本が保管されます。
したがって、公証役場に問い合わせれば、遺言検索システムを利用して、全国すべての公証役場での公正証書遺言の有無や保管先の公証役場を調査してもらうことができます。なお、検索の申し出は無料です。
また、秘密証書遺言と異なり、公正証書遺言は公証役場で原本が保管されているので、保管先の公証役場で実際の遺言書を閲覧・謄写することで遺言書の内容も明らかになります。

⑤ (公正証書遺言又は法務局保管の自筆証書遺言以外の遺言書がある場合) 遺言書の検認
遺言書の調査により遺言書が残されていることが判明した場合、相続人は被相続人の死亡後に家庭裁判所で「検認」という手続きを取らなければならず(民法1004条)、これ怠ると5万円以下の過料を科されることになります(もっとも、公正証書遺言と自筆証書遺言保管制度によって法務局で保管されている自筆証書遺言の場合は検認を経る必要がありません)。
検認というのは遺言書の内容や状態について家庭裁判所が確認し、記録化する手続きのことであり、遺言書の偽造や変造、滅失を防ぐための制度であるといわれています。
単に遺言書の内容や状態を確認するだけであり、遺言書が有効か無効かを判断する手続きではありませんので、検認をしたかどうかは遺言書の有効無効には関係ありません(検認をしても遺言の有効要件を満たさなければその遺言は無効ですし、逆に遺言の有効要件を満たしていれば、検認をしていなくても有効な遺言として扱われます)。
しかし、上述のように検認をしないと5万円以下の過料を科されるおそれがありますし、遺言書によって預金の払戻や名義変更をする場合は検認を経ていないと受け付けてくれませんので、必ず検認の手続きは経ておくようにしましょう。
検認手続きは相続人の誰かが家庭裁判所に申立てをすることで開始されます。申立先は、被相続人が死亡した時点の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立ての費用は遺言書1通につき800円です。
申立て後、家庭裁判所は、相続人に対して、遺言書が存在すること、家庭裁判所で検認手続きを実施すること及び検認手続きの日時などを通知します(もっとも、通知を受けた相続人は、検認の期日を欠席しても構いません)。
検認手続きの当日は、相続人立会のもと裁判官らが遺言書の状態や形状を確認し、写しを取るなどして記録化します。
検認手続きが完了すれば、裁判所の検認済証明書が添付された遺言書が返却されます。

⑥ (遺言書がある場合) 遺言書の効力と内容の確定
遺言書にはそれが有効であるための条件(遺言の有効要件)が民法で定めており、これを満たさない遺言書は無効となります。ですので、遺言書がある場合でもそれが有効か無効か問題になる場合があります。
また、遺言書自体は有効であったとしてもその意味するところが必ずしも明確ではなく、遺言書の内容を巡って争いになる可能性もあります。
このように、遺言書の効力や内容について争いが生じた場合、相続人間で話し合って解決できれば問題ありませんが、話し合いで解決しない場合は、結局、裁判などでその効力や内容を確定しなければなりません。

⑦ 遺産分割
有効な遺言書が残っており、そこに具体的な遺産分割の方法まで記載されている場合(例えば「居宅は妻に、山林は長男に、預貯金は長女に与える」など)は、その遺言書に基づいて遺産を分割することになります。
他方、遺言書が残っていない場合や遺言書はあるものの具体的な分割方法までは記載がない場合(例えば「遺産を妻に6、長男に1、長女に3の割合で与える」など)は、遺産をどのように分けるかを相続人間で協議して決める必要があります。
なお、遺言書がない場合、各相続人の相続分割合は民法の規定によって定められます。
相続人間での話し合いの結果、協議が調えば遺産分割協議書を作成し、全員が署名、押印します。
これに対して、協議が調わない場合は、家庭裁判所で調停ないし審判をする必要があります。

⑧ 財産の移転
遺言書に具体的な分割方法まで記載がある場合は、遺言書に基づいて預貯金の払い戻しや不動産の所有権移転登記が可能です。
他方、遺言書がない場合や遺言書があっても具体的な分割方法の記載がない場合は、遺産分割協議書によって預貯金の払い戻しや不動産の所有権移転登記を行うことになります。
相続手続きは弁護士にご相談を
相続手続きは非常に複雑であり、適切に進めていくには専門家の知識が必須になります。
また、感情的な対立が絡むケースも多く、当事者だけでは解決しないこともよくあります。
事件を迅速に解決するためには、早期に弁護士が間に入り、専門的な知識に裏付けられた調査、交渉を行うことが不可欠です。
相続手続きでお困りの場合はお早めにご相談ください。