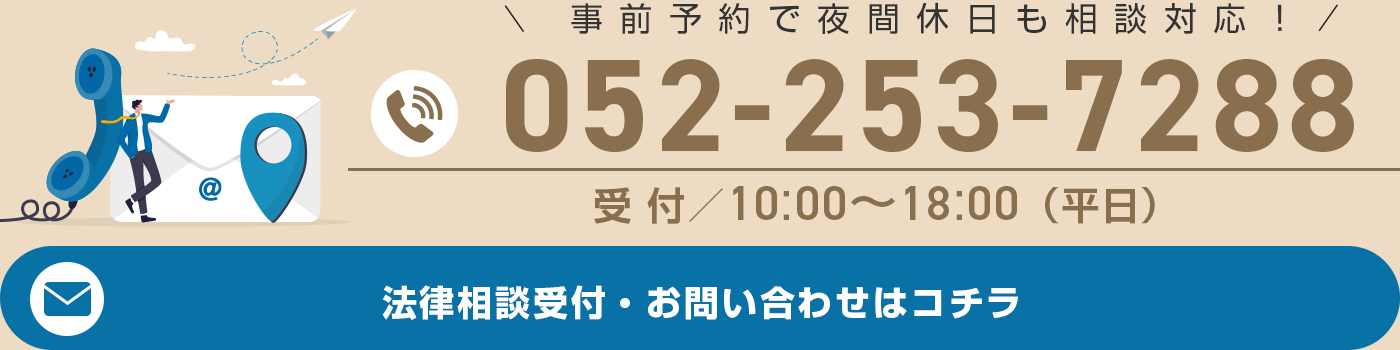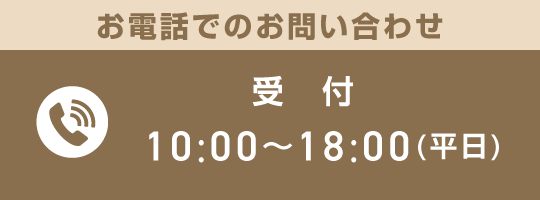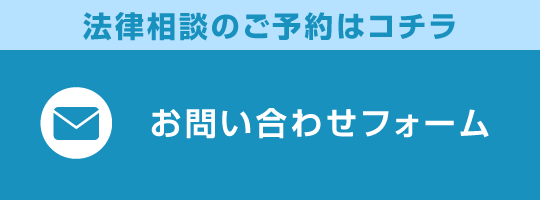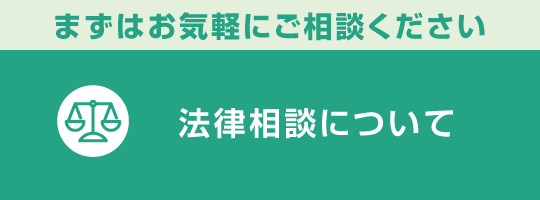このページの目次
揉めない遺言書の作り方を弁護士が解説します
自分の死後に残された家族が揉めないよう遺言書を作っておきたいという需要は年々高まりを見せてきています。
しかし他方で、遺言書があってもその効力や内容をめぐって親族間でトラブルになるというケースも多く見られます。
ここではせっかくの遺言書がトラブルの火種とならないよう、残された家族が揉めないための遺言書の作り方について解説していきたいと思います。
遺言書の種類
遺言書には① 自筆証書遺言、② 秘密証書遺言、③ 公正証書遺言の3つがあり、まずはどの遺言書を作成するのかを選ぶところから始めなければなりません。
そこで、最初にそれぞれの遺言書の特徴と作成方法、形式面での注意点を解説したいと思います(内容面での注意点は後でまとめて説明します)。
① 自筆証書遺言
自筆証書遺言のメリット、デメリット
自筆証書遺言とは、文字通り、自分で筆記し、署名押印する遺言書のことです。
作成にコストがかからない点、遺言書の存在や内容を秘密にできる点などがメリットになります。
他方、公的・中立的な第三書の関与がないまま作成されることになるので、後のその効力や内容について相続人間でトラブルになるリスクが相対的に大きいといえます。
さらに、作成に弁護士などの専門家が関与していない場合、方式違背で無効になっしまうリスクもありますし、紛失、滅失のリスクも避けられません(もっとも、この点は後述する遺言書保管制度を利用することで回避できます)。
なお、自筆証書遺言は、保管制度を利用した場合を除いて、相続開始後に検認を受けなければならず、これも一つのデメリットといえるでしょう。
自筆証書遺言の作り方
自筆証書遺言は「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と定められています(民法968条1項)。
したがって、全文を手書きで筆記した上で、日付と氏名を記入し、押印しなければなりません。これらの方式に違背した場合、遺言書は無効になります。
押印は実印である必要はなく、認めの印鑑でも効力に影響はありません。もっとも、自分の遺言書であることを確実に証明するためには実印で押捺した方が無難といえるでしょう。
なお、近時の法改正により、遺言書の別紙として財産目録を作成する場合、財産目録の部分だけはパソコン等の印字で作成できるようになりました。目録をパソコン等で作成した場合は、印字した紙面の1枚ずつに署名、押印をしなければなりません(両面印刷の場合は表と裏の両方に署名押印をする必要があるので要注意です)。
また、自筆証書遺言を訂正する場合は「遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」とされています(民法968条3項)。
したがって、単に二重線を引くなどして加除訂正し、印を押しただけでは修正の効果は生じず、そこにさらに「第3行中1字削除1字加入」や「第7行中3字加入」などと変更の旨を付記して、修正箇所全部に署名しなければなりません。
自筆証書遺言を修正する場合は、基本的には最初から作り直した方が無難といえるでしょう。
自筆証書遺言の保管制度
令和2年7月10日から自筆証書遺言の保管制度がスタートしました。
これは作成した自筆証書遺言を法務局で保管をしてくるという制度であり、この制度を利用することで遺言書の滅失や紛失のリスクはなくなります。また、保管にあたって遺言書が民法に定める形式を満たしているかどうかを確認してくれるので、方式違背で無効になるリスクもないといえるでしょう。さらに、保管制度によって保管されていた自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが不要になります。
他方、申請の手続きがやや面倒なので、自筆証書遺言の手軽さというメリットは低減するといえます。また、法務局で確認してくれるのはあくまで形式面だけであり、内容面を審査して何かアドバイスをしてくれるわけでもないので、遺言書の内容をめぐって争いにあるリスクというのは保管制度創設後も相変わらず残ることになります。
なお、申請の手数料は1通につき3900円です。
申請手続きの詳細については、法務省のホームページに詳しく説明されておりますので、こちらをご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
自筆証書遺言を作成する際の形式面での注意点
ア 直筆で書くこと
本文は全て自分で手書きしなければなりません。パソコンなどを使って書くことは当然できませんし、他人に代筆してもらうこともできません。
ただし、上述したとおり、財産目録についてはパソコンなどを使って印字で書くことができます。もっともその場合でも、全てのページに直筆の署名と押印をしなければなりません。
イ 日付を記入すること
同一人の遺言書が複数ある場合は常に一番新しいものが有効になります。また、遺言書を作成した時点で遺言者に十分な判断能力(遺言能力)があったことも遺言の有効要件となります。
このように遺言書はその作成した日付が非常に重要な意味を持つことになります。
そこで、遺言書には必ず作成の年月日を記入しなければならないと定められています。
ウ 署名と押印をすること
別人が作ったものでないことを示すために遺言書には必ず署名と押印をしなければなりません。
押印は実印である必要はありませんが、遺言作成者に相違がないことを示すためには実印を押捺した方がよいといえるでしょう。
エ 修正テープなどは使わないこと
上述のとおり、自筆証書遺言は修正する場合についても厳格に要件が定められており、これを守らないと修正は無効になるので注意しましょう。
オ 連名で作成しないこと
遺言書が無効になるパターンで多いのは、夫婦が連名で遺言書を作成してしまった場合です。
遺言書は必ず一人ずつ作成する必要があるので、夫婦で遺言書の内容について話し合った場合でも、別々の紙で作成するようにしましょう。
② 秘密証書遺言
秘密証書遺言のメリット、デメリット
秘密証書遺言とは、遺言者が自分で作成した遺言を封印した上で、それを公証人に提出 し、確認してもらう遺言書のことです。
自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な形態であり、遺言書の内容を秘密にできることやパソコンで作成できることなどのメリットはありますが、遺言書自体は自分で作らなければならず、公証人のチェックも入らないので、方式違背によって無効になるリスクがあります。
また、その効力や内容面をめぐって相続人間でトラブルになる可能性が相対的に高く、しかも自分で保管をしなければならないので紛失、滅失のリスクも残ります(自筆証書遺言のように保管制度も利用できません)。相続開始後は家庭裁判所で検認も受けなければなりません。
このように自筆証書遺言のデメリットの多くをそのまま引き継ぎつつ、手続きは面倒で費用もかかる(1通1万1000円)という制度設計のため、秘密証書遺言の利用件数は全国でも年間100件程度と極めて低調です。
秘密証書遺言の作り方
秘密証書遺言は作成した遺言書に署名押印して封筒に入れて封印することで作成します。封印の際に用いる印鑑は遺言書本文に押捺したものと同じでなければなりません。
封印した遺言書を公証人と(自分で用意した)証人2名に提示し、それが自分の遺言書であることと自分の氏名・住所を申述しなければなりません。
この申述を受けた公証人が遺言書の封筒にその日の日付と遺言者の申述を記載した後、遺言者・公証人・証人2人全員がその封筒に署名押印を行なって完成です。
完成した遺言書は遺言者に返還され、遺言者が自分で保管することになります。
自筆証書遺言を作成する際の形式面での注意点
ア 自筆の手書きでなくてもよい
秘密証書遺言は、財産目録のみならず本文もパソコンなどを使って印字で作成することができます。他人に代筆してもらうことも可能です。
イ 日付を記入すること
この点は自筆証書遺言と同じです。
ウ 署名押印をすること
署名押印が必要なのは自筆証書遺言と同じです。
署名は必ず手書きで自書しなければなりません。
エ 修正テープなどをつかわないこと
修正の方式は自筆証書遺言の場合と同じです。
オ 連名で作成しないこと
この点も自筆証書遺言と同じです。
カ 封印の際は遺言書と同じ印鑑を使用すること
秘密証書遺言は秘密証書遺言と違い、必ず封筒に入れる必要があります。そして、その封筒を糊付けして閉じ、その封じ目に押印をして封印します。その際、封印に用いる印鑑は遺言書本体に押印したものと同じでなければなりません。
これらの方式に違背した場合、秘密証書遺言としては無効になります。
もっとも、秘密証書遺言として無効になった場合でも、それが自筆証書遺言の形式を満たしていれば、自筆証書遺言として有効になる可能性はあります。
③ 公正証書遺言
公正証書遺言のメリット、デメリット
公正証書遺言とは、公証人が公正証書として作成する遺言書のことです。
公正証書遺言は、公的機関である公証人が作成するので、方式違背で無効になるリスクや効力をめぐって相続人間で争いになるリスクがほとんどありません。また、内容面でも公証人のチェックが入るので、他の二つに比べると内容をめぐってトラブルになるリスクも低いといえるでしょう。
さらに公証役場で保管してくれるので、滅失や紛失のリスクもありません。
揉めない遺言書を作成するという観点からすれば、間違いなく公正証書遺言がもっとも適しているといえるでしょう。
他方、作成に要する費用は他の二つの遺言書よりも高額になります。
公正証書遺言の作り方
公正証書遺言の作成方法については、次の関連記事で詳しく説明しておりますので、そちらを参考にしてください。
関連記事:「公正証書遺言の特徴と作成の流れ」
公正証書遺言を作成する際の形式面での注意点
公正証書遺言は公証人が作成してくれますので、遺言者において形式面で気を付けるべき点は特にありません。
遺言書が有効であるためには遺言能力も必要
ここまで有効な遺言書を作るための形式面について解説してきましたが、遺言書が有効であるためには、民法が定める形式を満たしていることに加え、遺言書を作成した時点で遺言者に遺言能力あったことが必要とされています。
遺言能力というのは、有効な遺言書を作成するための最低限の判断能力のことであり、これがないと遺言は無効になります(なお、民法では15歳以上であることも遺言能力として定められていますが、これが実際に問題になることはほとんどないでしょう)。
遺言をめぐる実際の争いでも「遺言書を作成したときにはすでに認知症が進行して判断能力がなかったので、遺言書は無効だ」などとして遺言能力が争われることが往々にしてあります。
遺言能力の有無は、遺言時における遺言者の精神障害、遺言書の内容などを踏まえて総合的に判断されます。
遺言能力をめぐって相続人間で争いにならないようにするためには、遺言時に遺言能力があったことを示す医師の診断書を残しておく、遺言作成時の状況を録音、録画しておくなどの対策が考えられるところです。
揉めない遺言書にするための内容上の注意点
最後に、揉めない遺言書にするために3種類の遺言書に共通する内容面での注意点を列挙しておきたいと思います。
① 遺産はできるだけ特定した方がよい
「不動産は全て長男に譲る」や「預貯金は全て妻に与える」などのように遺産を個別に特定しないような記載方法も可能ではあります。
しかし、このような書き方だと移転登記や預金の払戻しの際に手続きが面倒になります。
また、記載の仕方次第では遺産が特定できないとして、相続人間でトラブルの原因になる可能性もありえます。
不動産であれば登記簿謄本の記載事項、預貯金であれば金融機関名、支店名、種別、口座番号を記載するなどして、個々の財産を特定できるように記載すべきでしょう。
② 誰にどの財産を与えるかを明記した方がよい
遺言書では「遺産を妻に5、長男に3、次男に2の割合で与える」などとして、相続分を指定するだけの記載も可能です。
しかし、この書き方だと、誰がどの財産を引き継ぐかが決められておらず、結局、相続人間での遺産分割協議を必要となり、遺産をめぐって相続人間で新たにトラブルになる可能性があります。
したがって、揉めない遺言書という観点からは、誰にどの財産を与えるのかを明確に記載しておいた方がよいといえるでしょう。
③「相続させる」旨の遺言を活用する
遺言によって財産を与えることを遺贈といいますが、遺言書ではこの遺贈のほかに「相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言)も可能とされています。
「相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言)とは、文字どおり、特定の財産を特定の相続人に相続させることであり、法的な性質は遺産分割方法の指定であると解されています。
「相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言)がされた場合、原則として、相続開始時に何らの行為も要せず当然に遺産が相続人に移転すると考えられています(最判平成3年4月19日)。
したがって、例えば遺産が農地の場合は、「相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言)にすることで農業委員会の許可がなくても遺産を引き継ぐことができます(遺贈の場合は農業委員会の許可が必要になります)。
さらに、遺産が借地権の場合は、遺贈であれば賃貸人の承諾を得なければならないのですが、相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)にすることで賃貸人の承諾が不要になります。
また、相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)の場合、単独での登記申請が可能です。もっとも、これまでは遺贈の場合、受遺者と他の相続人との共同申請が必要でしたが、昨今の法改正により、令和5年4月1日からは相続人に対する遺贈の場合であっても受遺者による単独での登記申請が可能になりました(なお、相続人以外の者への遺贈については、依然として共同申請が必要です)。
したがって、この点での遺贈との差異は無くなったといえるでしょう。
以上のように、「相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言)が何かと便利なので、「遺贈する」ではなく「相続させる」という表現を用いたが方がよいといえます。
④ 遺留分を侵害しない遺言書にした方が良い
相続人の遺留分を侵害する遺言書の場合、遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求がされ、新たな紛争を生じさせるリスクがあります。
揉めない遺言書という観点からすれば、相続人の遺留分に配慮した遺言書の方が望ましいといえるでしょう。
もちろん、そうはいっても相続人との関係性やそれまでの経緯、生活状況などから、遺留分を侵害することになったとしても特定の相続人等に遺産を集中させたいという場合もあるかと思います(なお、遺留分を侵害する遺言書であってもその効力には何ら影響がありません)。
これについては、のちの紛争リスクとそのようなニーズを天秤にかけて遺言者の判断において決定されるべき事柄といえるでしょう。
⑤ 不安な場合は遺言執行者を決めておく
遺言執行者とは、預金の払戻しや不動産の移転登記、子の認知など遺言書の内容を実際に執行する人のことです。
遺言の内容がきちんと履行されるか不安な場合は、遺言執行者を定めておくのも有効な選択肢でしょう。
なお、預貯金の払戻しの場合、通常、預貯金の遺贈等を金融機関に対抗するための通知または承諾が必要になりますが、これには相続人の協力が不可欠です。したがって、相続人の協力が得られにくいような場合、預貯金の払い戻しをスムーズに行うことができないおそれがあります。
しかし、遺言執行者がいることで、遺言執行者により、受遺者等への名義書換え、払戻請求が可能になることから、スムーズに目的を達成することが可能となります。
このようなことからも遺言執行者を定めておくメリットがあるといえるでしょう。
なお、遺言執行者は個人でも法人でもなることができます。相続人の中から選ぶこともできますし、第三者を選任しても構いません。
⑥ 補充遺言を設定しておく
遺贈や「相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言)を定めていても、その対象となる人が先に亡くなった場合、その遺言は無効になってしまいます。
例えば、Aが自分の死後に妻Wが住む場所に困らないよう自宅不動産をWに遺贈する遺言書を残していたとしても、Aより先にWが亡くなってしまった場合、Wに不動産を遺贈するという遺言は無効となってしまいます。
そのような場合に備えて、遺贈や「相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言)の対象となっている人が先に亡くなった場合に、その財産を誰に引き継がせるのかを遺言(このような遺言のことを補充遺言といいます)により定めておくとよいでしょう。
遺言書の作成は弁護士に依頼を
遺言書の作成は相続制度全体を通覧する専門的な知識が必要不可欠です。
遺言書は自分一人でも作成することができますが、それによって無効な遺言書になってしまったり、却って親族間のトラブルの火種になったりする可能性もあります。
遺言書の作成をお考えの場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。
名古屋H&Y法律事務所では、1通11万円(税込)〜で遺言書の作成を承っております。
ぜひお気軽にご相談ください。