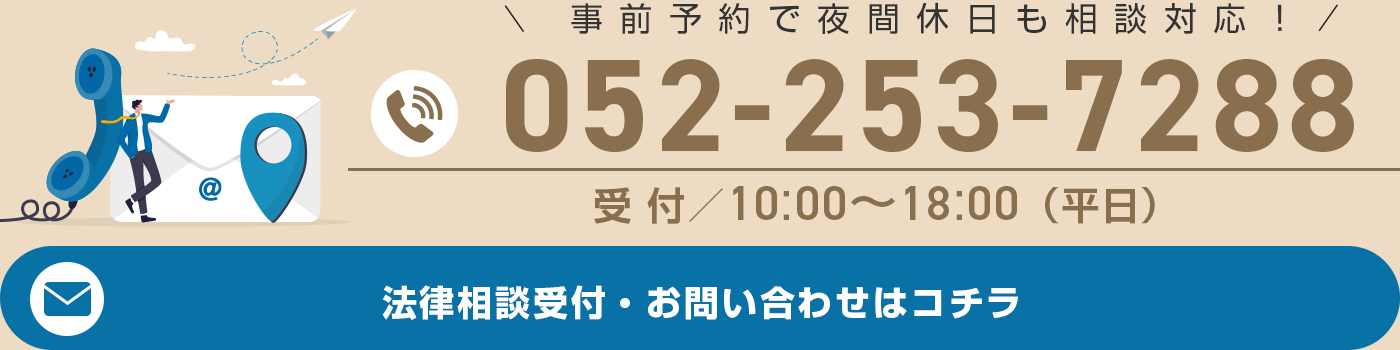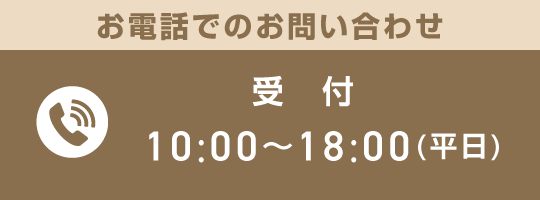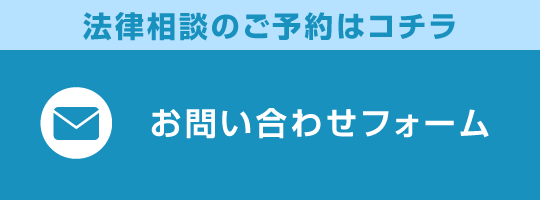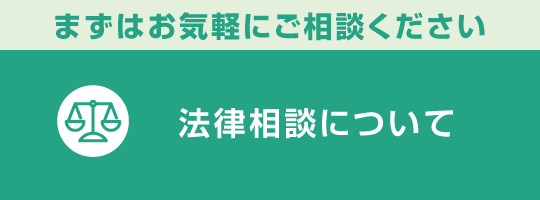このページの目次
遺産調査の方法について弁護士が解説します
親族が亡くなり遺産を相続することになった場合、その人がどのような財産をどれだけ有していたのかがわからないと遺産分割などの相続手続ができません。
また、亡くなった親族が多額の借金をしていた場合などは相続放棄を検討すべきですが、これも被相続人の財産状況がわからないと相続放棄をすべきか否かの判断をすることができません。
したがって、親族が亡くなった場合にまずすべきなのが被相続人の財産調査です。
ここでは遺産相続の対象となる被相続人の財産にはどのようなものが含まれるのか、また、被相続人の財産をどのように調査すべきかについて、弁護士が詳しく解説したいと思います。
相続する遺産の範囲は?
そもそも遺産相続の対象となる財産(遺産)にはどのようなものが含まれるのでしょうか?
これについては、民法に次のような規定があります。
第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
このことから次のことがわかります。
- 財産の対象となるのは被相続人が有する財産であること
- 被相続人が有する全ての権利と義務を相続すること
- ②の例外として、被相続人の一身に専属する権利義務は相続しないこと
順番に解説していきます。
① 被相続人が有する財産であること
→ 生命保険金や死亡退職金は遺産に含まれない
まず、被相続人が亡くなるときに有していた財産のみが遺産相続の対象となるのであり、被相続人以外の人が有していた財産は遺産相続の対象になりません。
「何を当たり前のことを」と思われるかもしれませんが、ここで問題となるのは、被相続人が自分を被保険者とする生命保険に加入していた場合です。
例えば、Aに妻Wと子X・Yがいたとします。Aは自分が死亡した場合のことを考え、死亡保険金を5000万円とする生命保険に加入し、その受取人をWにしました。その後、Aが死亡し、Wの口座に5000万円が振り込まれた場合、X・Yは自分たちもその5000万円について相続する権利があると主張できるでしょうか?
この点については、判例でX・Yは相続権を主張できないとされています。なぜなら、Wの保険金請求権は保険契約から生じるW固有の権利であり、被相続人Aの権利ではないからです。
つまり、被相続人が特定の相続人を受取人とする生命保険に加入していた場合、その保険金請求権は受取人に指定された相続人が取得する固有の権利であって、被相続人の権利ではないので、遺産には含まれない(=相続の対象とならない)ということですね。
なお、この点については、死亡退職金も同様です。すなわち、死亡退職金請求権は社内規定などによって受取人とされている相続人固有の権利なので、遺産相続の対象とはならず、受取人以外の相続人が権利を主張することはできないということです。
② 被相続人の全ての権利と義務を相続する
遺産相続においては、原則として、被相続人の全ての権利と義務を相続することになります。
ですので、不動産、動産、現金、預貯金、貸金債権、賃借権、有価証券などのあらゆる財産が相続の対象になります。
もちろん、プラスの財産だけではなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も相続することになります。
マイナスの財産の方が多い場合などは、相続放棄を検討すべきでしょう。
③ 一身に専属する権利義務は相続しない
②では全ての権利義務が相続の対象になると述べましたが、被相続人の一身に専属する権利義務は相続の対象になりません。
「一身に専属する」というのは難しい言葉ですが、大雑把にいえば「他の人がその権利を取得したり、行使したりすることが不可能または不適切なもの」のことです。
例えば、雇用契約上の地位がわかりやすいでしょう。会社勤めの被相続人が亡くなった場合、次の日から相続人が代わりに出社して働かないといけないかというと当然そんなことはありませんよね。
その他に、使用借権(物を無償で借りる権利)、代理権、委任契約関係などは民法上、死亡により消滅すると定められているので、相続財産には含まれません。
少し問題になるのが保証債務です。被相続人が誰かの連帯保証人になっていたような場合、相続人はその連帯保証人としての地位も相続するのかというと、答えはイエスです。
ただし、労働契約における身元保証債務は相続の対象とはならないとした裁判例があります(とはいえ、実際にこれが問題となることはほとんどないでしょう)。
一身に専属する権利義務の例
- 雇用契約上の地位
- 使用借権
- 代理権
- 委任契約関係
- 労働契約上の身元保証債務
相続財産調査の方法
遺産相続の対象となるのは、被相続人が死亡時に有していた全ての権利義務(一身専属権利義務は除く)ですが、実際に被相続人が亡くなったときにどのような財産を有していたかは必ずしも明らかでないことが多いでしょう。
そこで、遺産相続の対象となる財産の調査(相続財産調査)を行う必要があります。
その具体的な方法については、財産の種類によって異なるので、以下ではそれぞれの財産の種類ごとに解説していきたいと思います。
不動産
被相続人の生前の住宅など所在が明らかな不動産については、法務局で不動産登記事項を取得することで権利関係を調査することができます。なお、法務局に行かなくても、登記情報提供サービスや登記簿図書館などのオンラインサービスを利用して登記情報を取得することも可能です。
所在のわからない不動産については、遺品整理の際に被相続人の郵便物の中から固定資産税の納付書などが見つかればそこから調べることができます。
また、各市町村の固定資産税課に照会手続きをすることで、被相続人の不動産の名寄帳を取得することができます。つまり、その市町村内で被相続人が有している不動産を全てリストアップすることができるということです(なお、最近では登記簿図書館などのオンラインサービスにおいても名寄せ機能が実装されつつあり、これが利用可能になれば市町村に問い合わせなくても不動産のリストアップが可能になります)。
不動産評価額の把握については、固定資産税評価額による方法や路線価による方法、実際に不動産業者に査定を依頼する方法などが考えられます。
預貯金
まず金融機関を特定する必要がありますが、手がかりになるのは被相続人の通帳やキャッシュカードのほか被相続人宛の郵便物などです。金融機関から被相続人宛に郵便物が届いていた場合は、その金融機関に口座を有していた可能性が高いといえます。
金融機関を特定した後は、残高証明や取引明細を取得します。
他の相続人などによる遺産の取り込みが疑われる場合などは、少し費用がかかってしまいますが、お金の動きを確認するために取引明細を取得しておくべきでしょう。
なお、通帳やキャッシュカード、郵便物によって明確に金融機関を特定できない場合も、被相続人が生前通っていた金融機関がわかる場合は、その金融機関の口座の有無も照会しておくとよいでしょう。
動産、現金
動産(骨董品、絵画、貴金属など)や現金については、被相続人の遺品整理の際にその有無を調べるしかありません。なお、被相続人が貸金庫を契約している場合は、金庫内に保管されている可能性がありますので、金融機関において開錠の手続きを行う必要があります。
有価証券
株式などの有価証券については、証券会社や信託銀行からの郵便物が手がかりになります。また、株式の場合は、会社から株主総会招集通知や配当通知などが届いているはずなので、それらも調査の手がかりになります。
それらの郵便物から有価証券を保有していることが判明すれば、金融機関などに対して残高の照会を行います。
なお、郵便物が見つからない場合は、証券保管振替機構(いわゆる「ほふり」)に照会することで、登録済加入者情報を開示してもらうことができます。
借金
借金の有無についても、調査の取っ掛かりは郵便物などの遺品です。消費者金融から督促状などの郵便物が届いる場合は、被相続人が借入れをしていた可能性があるので当該消費者金融に問い合わせをすべきでしょう。
また、CIC(CREDIT INFORMATION CENTER)やJICC(株式会社日本信用情報機関)などの指定信用情報機関に信用情報の有無を照会することで債務の有無を把握することができる場合もあります。
その他の債権債務
貸金債権や賃借権などのその他の債権債務については、被相続人の遺品整理の際に契約書や督促状がないかをチェックすべきでしょう。
相続財産調査はいつまでにすればいい?
冒頭でも述べたとおり、相続財産調査の目的の一つに相続放棄をすべきか否かを判断するという点があります。
そして、相続放棄は被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内にしなければなりません。
したがって、相続財産の調査は遅くとも被相続人の死亡を知ってから3か月以内には完了させる必要があります(実際、相続放棄の申立てにも一定の時間を要するので2か月〜2か月半程度で完了させることが望ましいといえるでしょう)。
相続財産調査は弁護士への依頼がおすすめ
相続財産の調査は非常に煩雑であり、ご自身で行うことは困難でしょう。必要な調査が漏れてしまい、本来取得できるはずだった遺産が取得できなくなるといった事態も考えられるところです。
相続財産調査はプロの弁護士に依頼することをおすすめします。
名古屋H&Y法律事務所では、相続財産調査を最初に行い、相続財産の状況に応じて遺産分割の代理などに移行するか否かをお選びいただくプランもございますので、お気軽にご相談ください。