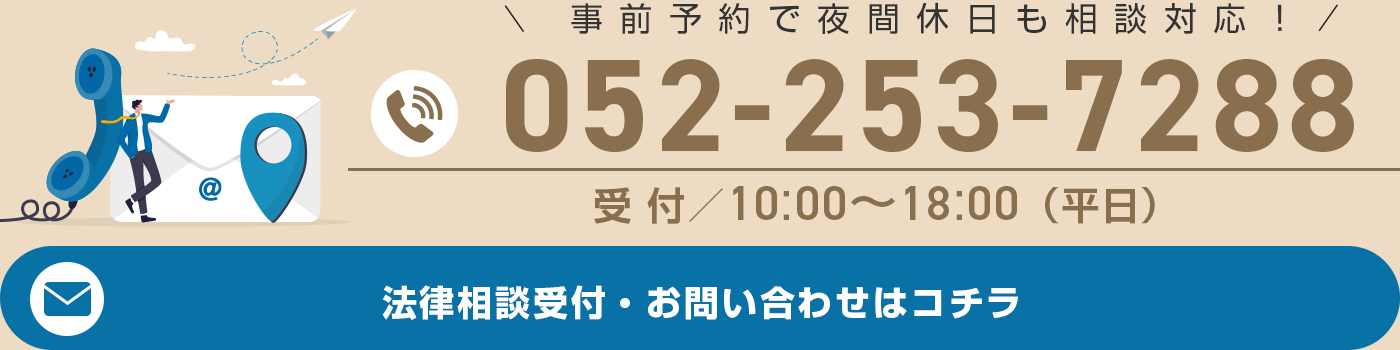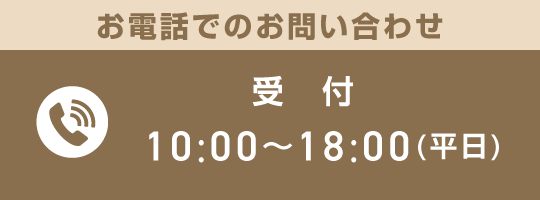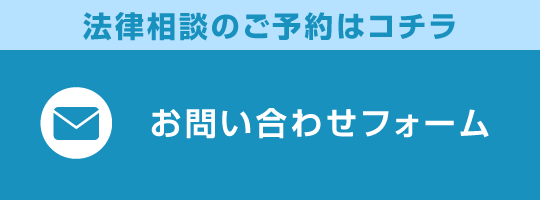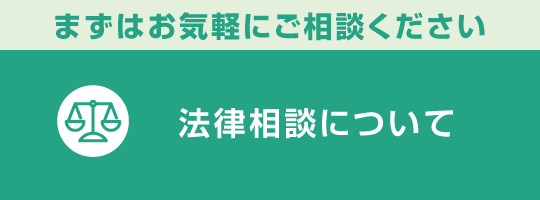このページの目次
そもそも「登記」って何?
不動産の「登記」とは、不動産の状況や権利関係を公に示すために、公的な帳簿である不動産登記簿にそれらの情報を記録し、公開する制度のことです。
よく不動産の「名義」という言葉をお聞きになることがあるかと思いますが、そこでいう「名義」とはこの登記の名義のことを指しています。
不動産登記簿は法務局で調整、管理されており、全国の不動産に関する情報を誰でも見ることが可能です。
登記がなぜ必要か?
なぜ不動産を登記する必要があるかというと、登記をしておかないと不動産に対する権利を第三者に対抗することができないからです。
どういうことかというと、例えばAさんがBさんから甲不動産を購入したとします。しかし、Aさんは甲不動産の所有権取得について登記をしていませんでした。
そうしたところ、Bさんが別のCさんに甲不動産を売ってしまい(二重売買)、Cさんは甲不動産の所有権取得を登記しました。
この場合、Aさんは最初に甲不動産を購入し、Bさんに購入代金を支払っているにもかかわらず、甲不動産の所有権を取得できず、甲不動産はCさんのものとなってしまうのです。
このように不動産に対する権利を保全するためには登記をしなければならず、これをしておかないと、知らぬ間に自分の権利を失ってしまうおそれがあるのです。
そして、これは遺産分割によって不動産を取得した場合も同様です。
後述するように昨今になって相続登記は義務化されていますが、それは別にしても不動産を相続によって取得した場合は必ず登記をするようにしましょう。
相続登記はどうすればいいの?
不動産登記は、登記申請書に必要書類を添付して法務局に提出することで行います。
もっとも、相続登記は、①遺産分割による相続登記、②法定相続分による共同相続登記、③共同相続登記後の遺産分割に基づく登記、④(相続人への)遺贈による登記などのパターンが考えられ、そのいずれであるかよって申請書の記載事項や必要書類などが異なります。
以下でそれぞれのパターンごとに解説していきたいと思います。
①遺産分割による相続登記
・申請人
通常、相続登記は登記権利者(権利を取得した人)と登記義務者(権利を譲渡した人)の共同で申請しなければなりません。
例えば、不動産の売買だと、売主と買主が共同で申請する必要があります。
しかし、遺産分割による相続登記の場合は、不動産を取得した相続人が単独で所有権移転登記を申請することができます(不動産登記法63条2項)。
・日付及び登記原因
登記申請書には登記原因(登記をする理由となった法的な原因)とその日付を記載しなければなりません。
遺産分割によって不動産を取得した場合、相続開始時に遡って不動産を取得するとみなされるため(民法909条)、申請書に記載する登記原因日付は相続開始日になります。
また、登記原因は「相続」です。
・登録免許税
固定資産税評価額の0.4%
・管轄法務局
不動産の所在地を管轄する法務局に申請書を提出しなければなりません。
・添付書類
ⅰ 登記原因証明情報
不動産登記の申請をする際は、登記原因の存在を証明する資料を添付資料として提出しなければなりません。
遺産分割による相続登記の場合は、被相続人との相続関係を示すために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等と相続人の現在の戸籍謄本が必要になります。
なお、法務局で承認を受けた法定相続情報一覧図を戸籍一式に代えることも可能です。
以上に加えて、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑登録証明書も登記原因証明情報として提出する必要があります。
なお、調停や審判による分割の場合は、調停調書や審判書を提出しなければなりませんが、この場合は、戸籍一式や相続人の印鑑登録証明書は基本的に不要となります。
ⅱ 住所証明書
不動産取得者である相続人の住民票を提出します。
ⅲ 委任状
司法書士等に登記申請を委任した場合は、委任状を添付しなければなりません。
ⅳ その他
その他、不動産の固定資産税評価額がわかる資料と被相続人の本籍地の記載のある住民票の除票を添付するのが登記実務となっています。
前者は登録免許税の計算をするため、後者は被相続人と登記名義人の同一性を確認するために必要であるといわれています。
②法定相続分による共同相続登記
・申請人
被相続人の死亡により相続は開始したものの遺産分割はまだ成立していないという段階において、不動産を含む遺産は相続人たちが法定相続分に応じて共有していることになります。
この共有状態について登記するのが「法定相続分による共同相続登記」です。
この登記は各相続人が単独で申請することが可能です。
・日付及び登記原因
登記原因の日付は相続開始日、登記原因は「相続」となります。
・添付書類、登録免許税、管轄法務局
添付資料は①で挙げたものから遺産分割協議書(または調停調書、審判書)と印鑑登録証明書を除いたものです。
登録免許税、管轄法務局は①と同じです。
③共同相続登記後の遺産分割に基づく登記
・意義
②の登記をした後で遺産分割が成立したことによって不動産を取得した場合の登記のことを指します。
・申請人
従来、不動産を取得した相続人と他の相続人が共同で「持分全部移転登記」を申請する必要があるとされていましたが、法改正により令和5年4月1日からは単独での「所有権更正登記」が可能になりました。
したがって、同日以降は、不動産を取得した相続人が単独で登記申請をすることができます。
・日付及び登記原因
登記原因の日付は遺産分割の成立日、登記原因は「遺産分割」となります。
・添付資料
ⅰ 登記原因証明情報
遺産分割協議書と相続人全員の印鑑登録証明書が必要になります。
なお、調停や審判による分割の場合は、調停調書、審判書を提出しますが、その際は印鑑登録証明書の提出は不要です。
ⅱ 住所証明書
申請者の住民票を提出します。
ⅲ 委任状
司法書士等に登記申請を依頼する場合は、委任状が必要です。
・登録免許税
不動産の個数×1000円
・管轄法務局
管轄の法務局は①、②と同じで不動産の所在地を管轄する法務局です。
④(相続人への)遺贈による登記
・申請者
従来、遺贈の場合については、受遺者と他の相続人との共同申請が必要とされていましたが、法改正により、令和5年4月1日以降は、相続人への登記の場合は受遺者による単独登記が可能になりました。
・日付及び登記原因
登記原因の日付は遺言者が死亡した日です。また、登記原因は「遺贈」となります。
・添付資料
ⅰ 登記原因証明情報
まず、遺言書が必要になります。
公正証書遺言や遺言書保管制度によって法務局で保管されていた遺言書を除いて、家庭裁判所での検認を経ているものでなければなりません。
また、死亡の事実の記載のある遺言者の戸籍謄本等及び受遺者の戸籍謄本等も登記原因証明情報として必要になります。
ⅱ住所証明書
受遺者の住民票の写しを提出します。
ⅲ 委任状
司法書士等に登記申請を依頼する場合は、委任状が必要です。
ⅳ その他
その他、不動産の固定資産税評価額がわかる資料と被相続人の本籍地の記載のある住民票の除票を添付するのが登記実務となっています。
不動産登記の義務化
令和6年4月1日から不動産登記の義務化制度がスタートしました。
これにより、相続によって不動産を取得した人は、相続開始があったことを知り、かつ、不動産を取得したことを知った日から3年以内に所有権移転登記の申請をしなければならなくなりました。
正当な理由がないのに登記を怠った場合は10万円以下の過料に処せられます。
なお、遺産分割協議がまとまらないなどの理由で登記申請ができない場合は、登記名義人について相続が開始した旨と自身がその相続人である旨を法務局に申し出ることによって、登記申請の義務を履行したものと扱われます(相続人申告登記制度)。
その後、遺産分割協議が成立した場合は、成立の日から3年以内に所有権移転登記を申請しなければなりません。
司法書士との連携態勢
不動産登記は司法書士の守備範囲であり、弁護士が登記手続きについて隅々まで知識を有しているわけではありません。
もっとも、遺産の中に不動産が含まれている場合、遺産分割や遺言書の作成をするにあたっては、常にその後の登記手続きのことも視野に入れておく必要があります。
そこで、登記のことも踏まえながら遺産分割や遺言書の作成を適切に行うためには、弁護士と司法書士の協力関係が必須です。
名古屋H&Y法律事務所では登記の専門家である司法書士をご紹介させていただくとともに、司法書士との密な連携体制に基づくリーガルサービスを提供させていただきます。
遺産相続や遺言書の作成のことでお困りの際はぜひお気軽にお声がけください。

名古屋市・伏見駅から徒歩1分の好立地にある当事務所では、企業法務から離婚や相続、交通事故まで、日常のさまざまなお悩みに寄り添ったサポートを行っています。
岡崎市、豊田市、豊橋市など愛知県内全域はもちろん、三重県・岐阜県の広い地域で対応。
不貞慰謝料や相続、刑事事件は相談料無料。リモート相談にも可能。事前予約で夜間・休日も対応いたします。
わかりやすく丁寧な対応で、法律をもっと身近に感じていただけるよう心がけています。
まずはお気軽にお問い合わせください。